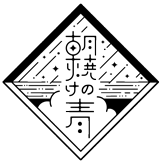梅雨が明け、徐々に暑くなり始めた土曜の昼過ぎ。食堂に降りると、良くんがボウルに缶詰をあけて何か作っているところだった。シロップのうす甘い香りが辺りに漂っていて、美味しいものが食べられそうな予感になんだかワクワクした気持ちになる。
「良くん、何してるの?」
「ああ慎か。ゼリー作ってるんだよ」
「ゼリー?」
「そう。七夕近いし、なんとなく懐かしくなって」
その言葉の真意が読み取れずに首を傾げていると、良くんが給食で出ただろ、七夕ゼリー、あれの話を梨奈としてたんだ。懐かしいよなって。
「そうなんだ」
「……そうだった、慎はあんま学校来てなかったもんな。七夕になると、給食で果物と、星の形をした寒天が入ってるゼリーが出たんだよ。あれ、梨奈が好きでさ。俺もなんか冷たいもの食べたいなって思ってたから、作ろうかと思って」
そう言って良くんはボウルにあけた缶詰の中身を指差した。そこにはフルーツミックスがたくさんあって、その横には小さい星の抜き型もある。
「このシロップを使ってゼリーを作るんだ」
「へぇ、美味しそうだね」
「できたら慎にも食わせてやるよ、多分美味しくできると思うから」
「あの、よかったら僕も手伝っていいかな」
「え、いいのか? そりゃ助かるけど……」
「七夕ゼリー、僕も作ってみたくなって」
「そっか、んじゃお願いするかな」
嬉しそうに良くんが笑った。寒天は前日にもう作ってあったらしく、あとは型抜きをするだけでいいらしい。良くんがゼラチンを溶かしている間、僕はその白い牛乳で作られたという寒天を星の形にくり抜くことになった。
ぷるぷると柔らかな感触の寒天はなんだか落ち着く懐かしい香りがして、僕は隙間を出来るだけ作らないように丁寧に寒天を星の形に抜き取っていく。
良くんはフルーツミックスのシロップを鍋に移して温めていた。うす甘いシロップの香りが少し強くなり始めたころ、そこにゼラチンを入れてゆっくりと木べらで混ぜていく。やがてゼラチンが溶け終わったらしい良くんは、鍋を火から下ろすと棚から青い小瓶を取り出してきた。
「今日はこれが使いたくてさ」
それはどうやら青い花から抽出されたという着色料らしかった。りんごの味がするらしいそれは、梨奈ちゃんがキラキラした目でねだったものらしい。
「夏の間にたくさん使ってやらないとな」
瓶の蓋を開けると、鮮やかな青い色からは想像がつかないりんごの香りがふわりと漂う。スプーンで掬うとジャムのようなそれはとろりと溶けて、とても美味しそうだった。それを室温に戻したサイダーの中に混ぜていく。シュワシュワと音を立てながら青い色に染まったサイダーは見るからに涼しげだ。それを粗熱をとったゼラチンの中に入れて混ぜ、ゼリーの型にフルーツと寒天と、その青いゼリー液を一緒に入れて冷蔵庫にしまう。夕食の時に食べような、と良くんが言ったので、その日はとても楽しみに夕食を待った。
そして待ちに待った夕食を食べ、良くん謹製のゼリーがお目見えになった。型から抜かれた青いゼリーは南国の海のようでとても綺麗だ。星型の寒天がひとでのように見える。けれど七夕ゼリーというからにはこれはきっと天の川なのだろう。天の川の中にはこうやって小さな星も混ざっているに違いない。冷たく燃える天の川の中の小さな星のことを考えながらゼリーを口へと運ぶ。パチパチと口の中で炭酸が弾けた。りんごの香りがほのかに漂うその七夕ゼリーは、夏の暑い夜に最適な、涼が取れて見目にも涼しい、この上なくぴったりな食べ物のように思えた。