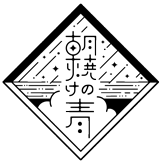遠くから小さくさざなみが聞こえる。星の燃える音さえも聞こえてきそうな静かな夜だ。耳をそば立てれば、柊と巡の健やかな寝息も耳に届く。自分の家の所有する別荘やプライベートビーチを友人と利用することは何度かあったが、ここまでありがたみを感じたことはなかったと思う。それだけ、このふたりが格別なのだ。大きくて柔らかなベッドに埋もれているふたりに近づくと、巡の髪をそっと手で梳く。しなやかで指になじむ質感に心が落ち着いていくのを感じて、意外と神経が昂っていたことを自覚する。
プライベートビーチに柊と巡のふたりを招待して、海を満喫した一日目の夜。すっかり体力を使い果たしたふたりは、夕飯もそこそこに寝室へ向かいベッドの上で横になることを希望した。部屋はいくつかあるが、と一通り見せて回ったところ、キングサイズのベッドがあるこの部屋を柊がいたく気に入ったので、ならば三人で川の字になり寝ようではないか、と提案したのだ。柊は最初こそ難色を示していたが、大きなベッドで眠ってみたいという好奇心に抗えなかったことと、ひとりでこの大きさのベッドを占拠することに罪悪感を覚えたらしいことから、巡を間に挟むことを条件に三人で眠ることを受け入れた。
そう決まると、柊は、ぼふ、と大きなベッドに寝転がって満足げに布団に顔をうずめた。よほど大きなベッドが嬉しいらしい。そんな様子を見ていると自然と笑みが溢れてくるのだから不思議なものだ。子に対する愛おしい気持ちというのはこういうものなのだろうか、と思う。
ふたりは部屋を決めると眠るために風呂へと向かい、各々痛む皮膚と格闘して入浴を済ませたようだった。特に巡は日焼けのダメージがひどかったらしく、ずいぶん長いこと浴室にこもっていたが、やがてどんよりとした顔つきで戻ってくるなりベッドにうつ伏せになると「薬を塗ってくれないか」とうめくように言ってきた。
「分かった、今取ってくるから待っていろ」
そう声をかけて部屋を出ていく。リビングにあたる部屋の隅に、管理人が用意してくれた薬の入った小箱がある。その小箱を手に巡のいる部屋へと戻り、ベッドに腰掛けると箱を開けた。とたんに真新しい消毒液の匂いが鼻腔に届く。中には新品の薬がいくつかと包帯、ピンセット等が入っており、箱の中の薬のパッケージを確認していくと、やけどや傷に、と書かれている薬があったので開封する。
「ほら、上着を脱いで背中をこちらに向けてくれ」
そう伝えるとのろのろと上体を起こした巡はパジャマの上着のボタンを外し、背中を晒した。本来であれば真っ白な肌が、日焼けで赤く腫れ上がっている。これはさぞかし痛いだろうと想像し、顔をしかめる。
「これは酷いな。赤く腫れ上がって火傷のようになっている」
「もうリンクユニットを割ってしまいたい気分だよ」
今は遠く離れている東成都の現状に想いを馳せる。今日から一週間ほどイーターの出現予想はゼロパーセントとなっており、つまり一週間はリンクユニットを割ることもないわけだ。恐らく一週間が経過する頃には通常の自己治癒力により完治するだろうが、それまでがひどく辛いだろう。
チューブの中から塗り薬を適量出し、指で取ると巡に「染みるぞ」と声を掛ける。ん、と返した巡の声が、指で触れた途端に息を飲むものに変わる。背中の皮膚が硬く緊張して、痛がっているんだということが言葉にされずとも分かる。できるだけ皮膚を擦らないよう慎重に巡の小さい背中に薬を塗り広げていくが、やはり辛そうで時折痛そうに引きつる皮膚に哀憐の情が湧く。
何度か励ましの声をかけつつ塗り進め、赤く腫れ上がった箇所すべてに薬を塗り終える頃には、巡はぐったりと疲れ切った様子だった。
「包帯も巻いておくか?」
「あー……いや、そこまでする程のことじゃない」
「しかしこのまま上着を羽織ると薬がすべて服に付いてしまう」
「……まぁそれはそうなんだが」
「大丈夫だ、予備ならあるぞ」
小箱に詰められていた包帯は全部で三つある。それらを見せると、巡はたかが日焼けなのに大仰になってしまうな、と乾いた声で笑った。
「大仰なものか、必要なことだ」
包帯の包みを剥がして巡の体へと巻いていく。巡に伝えたら怒られるだろうが、巡は小柄なので包帯もそこまで長さは必要ないように見えた。面積こそ少ないが引き締まった上体は、日頃の鍛錬の賜物だ。所々に残る傷跡も、巡のこれまでの戦いの記録だ。もちろん皮膚に残らなかった戦いもあるだろう。それらの戦いと、その戦いに引き込んだきっかけの言葉を思い出した俺は、それに意図的に蓋を閉めた。それでも手を止めることなく、動揺を悟られることなく巡の体へと包帯を巻いていく。やはり包帯は一般的に使用する長さと比較して大幅に余裕を残して巻き終えた。包帯をはさみでカットし、包帯クリップで先端を留めると、終わったぞと巡に声を掛ける。
「また手当てが上手くなったもんだな」
巡が肩周辺をゆっくりと曲げ伸ばしながら感心したように言う。
「そうだろう? 頼城さんはいつ何時、どんな場面でも頼れる男でありたいからな」
「ハハ、頼りにしてるぜヒーロー」
そう言いながらゆっくりとパジャマの上着を羽織る巡に背を向けて、使い終わった薬と余った包帯を小箱の中にしまっていく。
「さて、もう眠るといい。治りが遅くなるからな」
「ああ、そうさせてもらうよ」
ふあ、と大きなあくびをする巡を見とめると小箱を持って元あった場所へと戻しに行く。そこから帰ると、既に巡はベッドの中央で仰向けになってすやすやと眠っていた。その安らかな寝顔を見て心和ませていると、柊がやってきて「巡くん、もう寝てるんだ」と俺の背後からベッドを覗き込み、小声で呟いた。
「ああ、柊ももう寝なさい」
「紫暮は。寝ないの」
「俺は少しやることがあるからな、あとで眠るよ」
「……仕事?」
「まぁ、ちょっとした野暮用だ」
「……別にいいけど、休みの時ぐらい仕事、やめたら」
「なんだ、一緒に寝たいのか柊」
「違う……! もういい、巡くんと寝る」
小声で怒りながら柊は巡の元に行ってしまった。そっと、起こさないように慎重にベッドに潜り込むと、巡の方を向いて横になる。その大きなベッドは男子高校生ふたりが横になってもまだ余裕がある広さだった。これなら俺も共に眠れそうだ。柊がもぞもぞと佇まいを直しきった辺りで部屋の明かりを落とす。そのまま部屋を出ようとした時、部屋の中からおやすみ、と小さな声が聞こえた気がした。ベッドの方を振り返ったが、そこはさざなみの微かな音が聞こえてくるばかりの静かな部屋でしかない。まったく、柊は本当に愛らしい。巡を起こさないよう、おやすみ、と小声で返し、そっとドアを閉じた。
さて、仕事を片付けてしまわなければ。柊に言われた通り、休暇の時ぐらいと思い仕事を片付けてきたつもりだったのだが、副社長という立場柄、いつどこにいてもある程度仕事というものは舞い込んでくるものだった。
「やれやれ、格好がつかないな」
そう小さくひとりごちると、パソコンを置いてある部屋へと移動する。パソコンの電源を付けると、画面が明滅を繰り返しながら起動を始めた。その間に荷物の中から眼鏡を取り出して掛けると、すみやかに起動したパソコンの画面にパスワードを入力する。スマートフォンから既に内容を確認していたメールに添付されていた案件のファイルを開き、ざっと目を通すと、休暇中と告げていたにも関わらず届く案件だけあって、なかなか重要性のある内容だった。これは確認だけでも時間が掛かりそうだ、と思い時計を見る。腕時計が示している時刻はおよそ十時。もう柊も寝ついた頃だろうか。大きなベッドで寄り添ってすやすやと眠っているだろうふたりを想像して思わずふ、と笑みがこぼれる。少しだけ頑張ろう。そうしてあのふたりの待つ寝室へと向かうのだ。
カチリ、と送信ボタンを押して大きく伸びをする。やり遂げた達成感と、今日一日の疲労がない混ぜになって心地いい。時計を見れば二時を回ったところで、そろそろ眠るのには適している時間となっていた。
さて、と椅子から立ち上がる。音をできるだけ立てないように柊と巡が眠る部屋へと向かい、扉をそっと開いた。無音で開いた扉の向こうにすやすやと眠るふたりの姿を見とめた途端、ふっと肩の力が抜ける心地がした。息を潜めて近くにより、寝顔を確かめる。仰向けになって眠る巡と、巡の方を向く形で眠っている柊。ふたりを眺めているだけで深い安らぎが得られた。ここに連れてこられてよかったと心の底から思う。
しばらくそうしていると、巡がやや寝苦しそうにシーツの上で寝返りを打った。背中の日焼けが痛むのだろう。ウェットスーツを持ってくればよかったな、と少し申し訳ない気持ちになり、次いで背中の日焼け以外の傷痕を思い出した。それを作ったきっかけは、俺の誘いだ。巡にはもっと広い世界が必要だと思ったのは確かだが、別にそれは命を掛ける必要があるヒーローでなくともよかったのだ。あの時の選択は正しかったと胸を張って言えるかと問われれば、それは今でも分からない。その問いに対する答えは巡が生きて高校を卒業できるまで保留となる。背中いっぱいに包帯を巻いてもまだ余る小柄なこの体を酷使してイーターと戦い、訓練を重ねる。そうするようになってからよく感情が動くようになった巡は、別な道でもそうであったのではないかと、安全で生が約束された暖かな場所にいても同じ作用が起きたのではないかと、そう思った。
「すまないな、巡」
巡の顔にかかっていた髪をそっと手で梳いて横に流す。柔らかで乾いた質感に心が落ち着いていくのを感じる。
これはきっと夜だからだ。夜だからこんな思考に陥る。普段であればこんな後悔など口にしない。俺も、もう寝てしまおう。そう思った時、少しかすれた、なにがだ、という声がした。
「……起こしてしまったか、すまないな」
「……いや、いい、お前こそ何故起きてる……もう寝ろ」
まどろみから目覚めきっていない巡が、半分も開いていない目でこちらを見る。それと、とその掠れた声が続きを促す。
「なにがすまないんだ」
「……なんでもない、と言いたいところだが、お前にごまかしは効かないだろうしな」
巡がベッドから起き上がろうとしたのを、手でやんわりと制して戻す。巡の頭が柔らかな枕に沈んで、眠たそうに深く目が閉じられた。だから小さな声で、眠りを誘うように話しかけた。ついでに髪も撫ぜて、話の途中でどうか寝てくれないかと思いながら。こんなダサいところは、あまり見て欲しくはない。
「傷を見たんだ、腹や背についた沢山の傷を」
「ああ……そうだな、傷はあるが、それがどうかしたのか……」
「……俺が、誘わなければ付かなかった傷だと思って」
「……どうした、お前らしくもない……それに、思いあがるなよ」
今やっていることは、俺の意志だ、と巡がまどろみながら呟いた。分かっていた。巡ならそう返すだろうと。己のエゴだろうとも。けれど、この親友にもしものことがあったら、俺はきっと後悔する。そんなことにならないように祈りながら、巡の淡い色の髪を梳く。
「無茶はしてくれるなよ」
「それは俺の台詞だろう……お前も、無茶はするなよ……もう寝ろ……」
巡が頭を撫でていた俺の手を取って引いた。バランスを崩してベッドへと倒れ込みそうになるのをもう片方の手で支えて防ごうとしたが、なにせ片手が巡の頭付近にあり巡の髪を巻き込む恐れがあったため力が込められず、結局ベッドの中へと上体が崩れ込む。体を起こそうとしたが、巡の手がゆるやかに俺の頭に触れてそれを制した。
「……俺が、選んで決めたんだ……そうだろ、頼城」
巡の指が俺の髪を梳いた。そのまま手を頭の後ろに緩く回される。おやすみ頼城、と小さな声で呟いた巡は、そのまま眠りについたようだった。
頭に回された巡の手に触れる。俺より少しだけ体温が低いそれは、手のひらがゴツゴツしていて医学に携わる者の手とはかけ離れている。巡はとっくに覚悟を決めているのだろう。今の巡はあの日の巡ではないのだ。
じわじわと指先に染みる巡の体温に満ち足りた心地になった俺は、おやすみ巡、と呟いて目を閉じた。人と一緒に眠るなど何年ぶりのことだろう。幼い頃の両親との記憶が蘇る。温かで、鮮烈で、穏やかな記憶だ。遠く小さく聞こえるさざなみと巡の体温が混ざり、まどろんでいく。明日はどんなことをしよう、巡が笑ってくれるといい、ああ、楽しみだ。