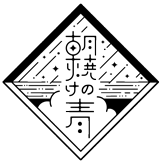パーティを開くと前日から言っていた通り、頼城は朝食が済んだ談話室兼食堂に業者を連れ込んであっという間にパーティ会場を作り上げてしまった。花が至るところに飾り付けられ、陽気な風船が並び、お抱えのシェフによる立食形式のあれこれが運び込まれ、気がつけば小規模な楽団までいて陽気なアイリッシュを流し出す始末だ。
「さあ巡、パーティの始まりだ!」
「ハハ、いや覚悟はしていたが毎度毎度すごいな……」
「『ホームパーティがしたい』というお前の希望だからな、今年は会場を貸し切ることはせず、俺たちのホームである合宿施設でのパーティにしようと思ったんだ」
「ああ、お前のホームパーティの規模を見誤っていた俺のミスだな」
会場を見渡せば今日の当直である頼城や柊、指揮官さんのほかに、今日は非番の伊勢崎さんや透野までいる。どうしたんだと話を聞けば、招待状をもらったんだと胸を張られた。いや、まあ、学校があるんじゃないかという話がしたかったんだが、まあいい。真面目な他の白星の連中がいないのはその辺が関係しているんだろう。
「あ、誕生日おめでとうございます、斎樹さん」
軽快なアイリッシュの音楽に負けないように声を張って、三津木が話しかけてきた。
「やあ三津木。今日は当直だったか」
「そうなんです。これ、よければどうぞ」
そう言って差し出された包みを礼の言葉と共に受け取る。
「悪いな、ありがとう」
「いえ、斎樹さんにはお世話になっているので」
中身、万年筆の手入れに使える溶剤なんです。と三津木は言った。金属が腐食しない成分で、インクの溶解に適している配合を試したんだとか。
「それは助かるな、ありがとう。使わせてもらうよ」
「ああいた、斎樹くん。誕生日おめでとう」
聞こえた声に顔を上げると、人の合間を縫って久森がこちらにやってくるところだった。辿り着いた久森は大きく息をついて人が多いねぇと呟くと、これを、と包みを掲げた。
「やっぱり斎樹くんには紅茶かなって思ったんだけど、でも良いもの知ってそうだし僕なんかが知ってるメーカーのじゃ駄目だよねって思ったから、紅茶に合いそうなお菓子を買ったんだ。口に合うといいけど」
見ればどこぞのパティスリーのものと思わしき包装の中に、焼き菓子がいくつか詰まっている。ふわりと漂うバターの香りは上品で新鮮だった。
「そんなことはないと思うが……ありがとう、大事に頂くよ」
そんなことを話している内に曲が終わった。パチパチと拍手がまばらに響くのに合わせて手を鳴らしていると、次の曲が掛かり始める。それと同時に、柊のちょっと! という声と、頼城の笑い声が響く。
「折角のパーティなんだ、踊ろうじゃないか!」
「ほん、ほんっっっとうに無理!」
見れば頼城が柊の手を取って部屋の中央でクルクルと踊っている。柊は顔を真っ赤にしながら、逃げることも叶わず頼城のリードに合わせて恥ずかしそうに回っている。あー、と思いながら見ていると、伊勢崎さんが透野の手を取って中央に躍り出た。頼城の見よう見まねでお互いの片手を取って、その手を中心にクルクルと回っている。楽団の人たちや招かれたのだろうアライブの大人たちは楽しげにワアワアと歓声を上げていた。
「あー、すまない三津木、久森、少し行ってくる」
「あ、はい! どうぞ」
「いってらっしゃい」
いたたまれない様子の柊と上機嫌な頼城の間に歩み寄ると、こちらを向いた頼城と目配せをしてハイタッチと共に柊と入れ代わる。今日の主役が出てきたとなって楽団は曲を盛り上げて指笛まで鳴る始末だ。頼城はこれ以上はないというほどに笑っていたし、俺もつられて苦笑いをして頼城の手を取って踊った。ちらりと柊の方を見ると三津木たちの方に向かっていって、何か三人で話しているようだった。ひとまずこれでよし、と胸をなで下ろす。テンポアップした曲に合わせて頼城が俺の手を取ってクルクルと回り出した。それに振り回されるようにグルグルと回り、伊勢崎さんや透野の心底楽しそうな笑い声と、いつの間にか混ざってきた指揮官さんと神ヶ原さんのコンビにぶつからないようにしながら踊って、踊って、踊った。踊っているうちに自然と口角が上がっていたらしく、ひと段落つけましょうという体で曲が終わった頃には頬の筋肉が痛くて痛くてしょうがなくなっていた。伊勢崎さんなんかは笑いすぎてお腹が痛いと地面に倒れ込んでいたし、指揮官さんと神ヶ原さんはもう無理、もう無理と笑いながらつったらしい二の腕や腰を労りあっていた。
楽団が流す音楽が穏やかなものに変わって立食パーティが主体になった頃、柊がそばに来てさっきはありがとう、と袖を引いた。
「ああ、いや、でも余計な世話だったか?」
「ううん、俺は俺で楽しかった。隅の方で少し、慎と踊った」
「そうか、ならよかった」
俺が上がったまま元に戻らない頬を押さえて軽く揉んでいると、柊がこれ、と言って包みを渡してきた。
「中身、バイオリンの弦。……また、巡くんの演奏、聞かせて欲しい」
「ああ、ありがとう。そうか……しばらく弾いていないな。今度付き合ってくれ」
ん、と言いながら嬉しそうに頷いた柊に穏やかな気持ちになる。少し食べて回らないか、と言って色々と出ている食べ物をつまんで回る。流石にどれもこれも美味く舌鼓を打っていると、頼城が楽しんでいるか、とやってきた。
「巡、これを」
頼城が差し出して来たのは薄い書類程度の大きさの包みだった。こいつにしてはコンパクトだなと思い、内心ホッとしながら受け取る。
「ああ、ありがとう」
「中身はカタログギフトになっている。好きなものを好きなだけ選んで注文してくれ」
「……カタログ? 紫暮が?」
いぶかしんだ柊が後ろから覗き込む。紫暮はにこやかに微笑んだ。
「いや何、最初は家を建てるつもりだったんだが止められてな」
「……家」
「……一応聞くが、なぜ家なんだ」
「巡がホームパーティがしたいなどと言い出すからな、感激してまず理想の家から作ろうと思ったんだ。だが巡の条件を聞かずに勝手に家を建てるのはどうかと思い今回は見送った」
「そうだな、うん、それで正解だ」
「つまり、巡の要望が聞けさえすればいい訳だ。だからカタログギフトの体勢を取った。ああ、もちろん問い合わせさえしてくれれば大体のものは実際に見ることが叶うぞ」
「……つまりなにか? このカタログギフトは家の目録なのか?」
「家も含まれるな」
「馬鹿なの?」
「俺はいたって真面目だぞ」
巡は愛おしい家族だからな、と目を細めてくる紫暮に苦笑いで返す。こいつの規模感はまるで分からない。
「誕生日おめでとう、巡。お前と共にいられることを、俺は心底嬉しく思っている」
「ああ……ありがとう。まあ、気持ちはありがたく受け取っておくよ」
そのストレートな祝いの言葉が面映くて少し視線をそらす。こういう事を相手に伝えることが恥ずかしいなどという感情とは無縁なんだろうな、きっと。
簡易的なステージの上では司会進行を務める誰かしらがビンゴマシーンを運んできていた。ビンゴだ! と伊勢崎さんの歓声が上がる。楽団もそれらしいBGMを流し出すから、場は一気にゲームムードになっている。まだまだパーティは盛り上がりそうだ。今日はもう休む暇のなさそうな表情筋がまた上がるのを感じて、まばゆいばかりのパーティ会場に手を引かれて飛び込んだ。