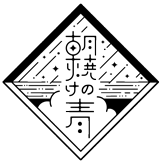春になると至る所で赤色の商品を目にする機会が増える。桜、いちご、あるいはその混合といった具合に、春の訪れを知らせる商品には赤もしくはピンクが適しているらしい。愛飲している紅茶メーカーのwebサイトにも季節限定のベリーを使用した紅茶が並んでいて、これはうっかりというか、なんというか、柊の顔が頭によぎりつい買ってしまった。そしてつい先ほど届いたのがこちらの商品という訳だ。銀色の缶に入った紅茶葉は、開けると弾けるようないちごの香りがした。甘酸っぱい赤い果実のそれは、なるほど春を嗅覚に訴えかけてくる。早速飲んでみようと階下に降りると、珍しいことに頼城がいた。コーヒーメーカーを前にして手を口に当てて何事か考え込んでいる。嫌な予感がする。
「おい、まさかお前コーヒーメーカーを壊すつもりじゃないだろうな」
「ああ巡、ちょうどよかった。コーヒーの淹れ方を教えてくれないか」
「いいから座っていろ、お前がコーヒーを淹れるのをハラハラしながら見守るのはごめんだ」
とりあえず頼城を椅子に座らせるとコーヒーメーカーが壊れていないか簡単に点検をする。入れてはいけない所に豆や水が入っていたりなどはないようだ。電源もきちんと入る。ひとまず安心して、頼城が好んで飲んでいるコーヒーの豆を棚から取ってきてミルで挽く。ゴリゴリキィキィとミルを鳴らしながら頼城の方を向くと、小さな包みが手元にあるのが見えた。よく見ると薄い和紙で包まれたそれはどうやら和菓子のようだった。
「珍しいな、お前が好んで菓子を食うのは」
「ああ……ふふ、桜もちなんだ。懇意にしている和菓子屋の店主が今年も販売を開始したと知らせてくれてな」
目を細めて包みを見つめる様子は子供のように嬉しげで、なるほど一年ぶりの好物を前にするとそんな幼い顔もするのかと少し驚く。ミルを挽き終えたのでコーヒーメーカーにフィルターをセットして、その中に先程の豆を入れて蓋をしめる。コーヒーサーバーを洗い、タンクに水を入れてスイッチを押せばコーヒーは自動的に美味しく抽出されるというわけだ。俺も料理が得意な方ではないからこういう物の存在はありがたい。コーヒーが抽出される合間にケトルに水を注ぎ、ガスの火を入れる。茶器を揃えて茶葉の蓋を開けると、頼城が珍しいなと声を掛けてきた。
「いちごの紅茶か? こういったフレーバーの類を好んでいたとは知らなかった」
「ああ、いや……なんというか、柊の顔がよぎって、つい」
そう応えると頼城が楽しそうに笑った。春先はいちごの商品が目白押しでつい選んでしまうな、と返ってくるところを見るに、頼城も似たようなことがあったのだろう。沸いた湯で茶器を暖めてから茶葉を入れ、再度湯を注ぐと、いちごの香りはより一層華やかに食堂に行き渡った。砂時計を逆さにしてから、抽出が終わった頼城のコーヒーをカップに注いで差し出す。
「ありがとう巡」
コーヒーを前にした頼城がおもむろに和紙の包みを開いていく。落ち着いた緑の葉に包まれた桃色の菓子がふたつ、並んでいた。
「ひとつどうだ」
「遠慮しておくよ。お前が全部食べるといい」
砂時計が落ち切ったのを見計らってカップに中身を注いでいく。普段飲んでいる紅茶より幾分赤いそれは、どうやら一緒に入っている赤い花びらの色素が作用しているものらしかった。頼城はそれ以上押し問答は続けず、その桃色の菓子を口に運んだ。もぐもぐと咀嚼しているその表情は心の底から幸せそうだ。
そういえば、春が好きだったなとふと思い出す。こいつも、柊も、そろって春が好きだと言っていた。自分はどちらかといえば冬を好んで、春は自分の誕生日があるからそこまで好きだと思えないでいた。けれど、こうして普段は選ばない春のものを選んでいる。それがなんだか不思議だった。
外を見れば青々とした葉が生い茂り、空が青く、花が咲いている。確かに春が巡っている。気が遠くなるような事実だ。紅茶を口にすれば、甘酸っぱい香りが鼻を通っていった。いちごの紅茶はなるほど、春先に合う風味のそれで、確かにおいしい。
今年は春にちなんだものを多く選択するのかもしれない、と予感じみた思考をする。それがなんだか嫌な気分ではなかった。思わず笑みの形に口が作られるのを、どこか人ごとのように思った。