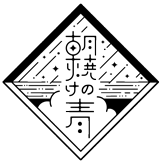ぜいぜい、ヒューヒューと喉が鳴る。息が苦しい。仰向けに寝ていることも横向きになることも苦しくて、寝返りばかりを繰り返す。ゴホゴホ、と喉の奥からせり上がった咳が静かな部屋の中に残響を伴って、時計の秒針の音と混ざって不健康で寂しい空間だと錯覚する。ここは合宿施設で、病院ではない。タッタッと鳴る秒針の音に、暗い部屋に、響く残響に医療施設を思うのは錯覚なのだ。早く寝てしまわなければ明日のパトロールに響いてしまう。そう焦るのだが、そんな状態でうまく眠れるはずもなかった。目蓋を開けばほんの少し重たさを感じるものの、眠るには至らない程度でしかない。
諦めて眠れない体を横向きにし、携帯を開けばメッセージアプリにいくつか未読の通知が届いていた。開くとそれは頼城からで、内容は他愛ない業務連絡だった。既読状態になってしまったため、指を動かして返信を打つ。「了解した」それだけの簡素な内容を打ち込んで送信する。残りの通知はグループチャットの内容で、これは目を通しておくだけでいいかと思い眺めていると、コンコンと控え目に部屋の扉が鳴らされた。
「……巡? 入るぞ」
音量をいつもより控え目にした呼びかけと共に扉が開かれ、廊下の光が室内に差した。眩しくて目が開けられないでいると、それを察していたのだろう扉を開けた人物が急いでぱたりと後ろ手に扉を閉める。頼城だった。
「……こんな夜更けにどうした」
出した声は少ししゃがれていて、喉が空気に触れて咽せるような咳が出た。
「柊から体調が優れないと聞いている。まだ眠れていないようだったから、薬を持ってきた」
「……そうか」
頼城はベッドサイドに来てしゃがみ込むと、手にした薬剤包装シートから二錠取り出し、俺の手のひらに乗せた。舌の上で溶かして飲むタイプだというそれは、口の中に入れるとほろほろと溶けて涸れた喉に清涼感を伴って染み渡っていく。しばらくすると幾分呼吸が楽になってきて、喉のかすれた音もしなくなった。
「すまない頼城、大分楽になったよ」
「ならよかった。では俺は早々に立ち去ろう。よく眠れるといいな」
「……頼城」
「ん? どうした巡」
部屋から出ようと立ち上がりかけた頼城に声をかけてしまい、立ち止まった頼城に、しまったと思う。特に、何かあるわけではなかったのだ。だが、秒針と咳の音の孤独な部屋を思うと、つい声をかけてしまった。少しその行動が子供じみていて恥ずかしくなり、頬に熱が通うのを感じる。
「……いや、なんでもない」
「……どうした? 何でも言ってくれ」
頼城は再びしゃがみ込むと、俺の手を取った。暖かい。それに少しほっとしながら、言葉に出来ることが何もないことに困っていた。きっと言葉にすれば今の頼城はなんでも聞いてくれるのだろう。けれど、この心の寒さを、名前を呼んで呼び止めてしまうような気持ちを、手の暖かさに救われるような気持ちをなんと言えばいいのか分からなかった。分からなかったから、手を握った。自分のゴツゴツとした手のひらの下、頼城の爪と骨の感触が伝わってきた。少しだけ時間を置いて、それらが動いて俺の手を握り返す。
「なんでもないんだ」
「そうか」
頼城が立ち上がり、ベッドに腰掛けたかと思うと俺を抱きしめた。手のひらよりももっと暖かい熱に触れて、寒さが溶け出したような錯覚を持つ。頼城の肩口に顔を埋める体制になったから、そのまま頭を預けてしまう。とろとろと心の中が暖かくなっていく。真夜中の暗がりはもう寒々しいものではなく、安らぎを与えるものに変わっていた。らいじょう、と名前を呼ぶ。どうした巡、と背中の方から声がした。
「大丈夫だ、もう」
「そうか」
熱が離れていくのをほんの少し名残惜しく感じながら、自分ひとりでも大丈夫だという確信を持って見送る。頼城の眼差しは優しかった。うっかり出てきたあくびを、頼城はもう眠れそうだなと言って笑って髪を梳いた。
「じゃあ、巡、良い夢を」
「ん……お前も、早く寝ろよ」
「ああ、ありがとう」
再度光が差して閉じられた扉を見送る。タッタッと鳴る秒針は、もう不安をあおるものではなく、規則正しいメトロノームのように眠気を誘うものになっていた。暖かな布団の中でそれを聞きながら目を閉じる。呼吸は楽で、寒くなく、暖色の闇に安心した気持ちで俺は眠りについていった。