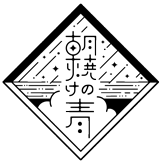※モブが出ます
今日は特に訓練の予定もない。イーターの出現予報もない。学校から帰り、簡単な宿題をし、夕飯までの間自室でぼんやりとしていた。
窓の外を眺める。秋口だから広葉樹が徐々に黄色や赤に葉を染めている。今日は天気がいい。最近涼しさを増していた気温も、今日は過ごしやすい温度になっている。
(少し、庭で本でも読むか)
新しく取り寄せていたものの読む暇がなかった学術書を一冊手に取ると、庭に出る。やわらかく吹く風が心地いい。
噴水の近くに備え付けられているベンチに腰掛けて表紙をひらく。幼少期から馴染んだ英語の羅列を懐かしいような気持ちで追っていく。
幼少期、この手の学術書を絵本がわりに読んでいたのでこの堅苦しい言い回しの英単語を読むと懐かしさが湧き上がってくる。正しく意味が伝わるように、正しい事実を記せるように書き手の配慮が施された学術書が好きだ。とはいえそういったことに気づけるようになったのは自分で論文を書くようになった頃の話だ。幼い頃はただただ新しいことを知るためだけに学術書を読んでいた。書き手の配慮や苦慮などということにはまるで気づいていなかった。自分で書いてみなければきっと分からなかったことだろう。
「おや、巡ぼっちゃん」
ふいに声をかけられて振り向く。そこには薄汚れた帽子とつなぎを着て、タオルを首にかけた老人がひとりいた。確か、この者は。
「あーっと……庭師、の方だったか」
「ええ、ええ、そうです。野中といいます」
野中さんは首にかけたタオルでひたいの汗を拭うと軽く背中を伸ばした。竹ぼうきとちりとりを持っている。
「ぼっちゃんが庭においでとは珍しい。いや今日は過ごしやすいですからな、いいことです」
「野中さんは、ずっと掃除を?」
「いえいえ、午前中は枝を切っておりました。生垣の切りどきですからね、冬に入る前に整えて切るんです。今はその枝を集めております」
確かに、言われてみれば庭を覆っている生垣が綺麗に刈られている。大きなズダ袋のようなものに枝が入ったものもいくつか散見された。
「それは大変だったな、ありがとう」
「とんでもないことです。巡ぼっちゃんは、今日はお仕事の方は?」
「今日は学校以外に用事はなくてね。のんびり本を読ませてもらっている」
かかげた本を野中さんに見せると、野中さんは何度もゆっくりと頷いて顔をほころばせた。
「ああ、それはいい。ぼっちゃんは昔から本が好きでおいでだったから」
「昔から……野中さんは、何年ぐらいこの庭の手入れを?」
「もう、何年もしております。ぼっちゃんが生まれる前からですかね、ずっとです」
野中さんがどこか懐かしむように庭を眺めた。リンドウ、コスモス、ダリア、キキョウ、バラ。見事な秋の花が咲き誇る庭は美しかった。きっと季節が巡るごとにきれいな花を咲かせていたのだろう。
「あ……すまない、その、昔は研究に没頭していて」
「いいんですよ、ぼっちゃんが一生懸命なのは存じていましたから」
幼いころは庭の花を見ることもなかったし、外国に住んでいたから、この家の庭の手入れをしている人間のことなど知らなかったのだ。庭とは、ただ外に出る門の途中にある敷地で、研究所がある土地で、そこに咲く植物に対しての感慨など特に持ったことがなかった。
「ぼっちゃんが庭に降りて来ることもあまりあることではなかったですからね。最近はよくお笑いになることも増えて、お声をかけやすい雰囲気になられた」
「……そうか? よく、笑っているだろうか、俺は」
「昔に比べれば、うんと笑っておいでですよ」
野中さんが笑って頷いた。そう、なんだろう。きっと。ヒーローを志すようになって、騒がしくなって、大声を出すことが増えて、きっと笑うことも増えたのだろう。
「そういえば、お見せしたことがなかったですね。こちらに来てください。ぼっちゃんの庭があるんですよ」
「俺の、庭?」
野中さんがゆっくりと歩き始めた。生活スペースと研究所の間にある庭の隙間、そこに俺の庭はあった。
レンガで区切られたいくばくかの土地、そこに色とりどりのガーベラが咲いていた。その奥には低木がいくつか植えられている。
「クチナシとガーベラです。ぼっちゃんの誕生花なんですよ。ぼっちゃんがお生まれになってから、私がここに植えました」
「……知らなかった。庭に、こんなスペースがあったのか」
「今、お教えしましたから」
野中さんがいたずらに成功したように笑った。
「本当はペパーミントも植えたかったんですがね、あれは寄せ植えには向いていない」
しゃがみこんでガーベラの花に手を添える。瑞々しく張りのある花弁がよく手入れされているのを物語っている。土は水の匂いがして、葉枯れもない。
「春になったら来てください。クチナシの香りがいいですよ」
「……教えてくれてありがとう、春になったら、また来る」
「ええ、ええ、ぼっちゃんの庭ですから、お好きにして下さいね」
日が落ちて、野中さんと別れたあと庭のことを考えた。きっと毎日、野中さんが水をやって、肥料を与え、剪定をし、掃き清め、虫の駆除をしていたのだろう。何年も、何年も。俺が死のうとした日だって、ヒーローとして初めてイーターと対峙した日だって、野中さんはこの庭に水を与えた。そうしてこの庭は成り立っていた。自分の家の庭なのに、きっと俺は初めてこの庭を見た。
結局表紙を開くことしかしなかった学術書のページをめくる。懐かしい文体だ。正確にものごとを伝える堅苦しい言い回し、たまに出てくる研究者の茶目っ気、新しいことを知れる有意義な内容。それを構築するためにどれほどの配慮と苦慮がなされているか、俺は知っている。
この庭だってそうなのだ。いや、恐らくあらゆる物事はそうで、たくさんの配慮と苦慮と、思いやりや努力の積み重ね、そうしたもので成り立っている。この庭だって例外ではなかっただけに過ぎない。
外を見ると夜空は晴れ渡っていた。星々と月が民家の屋根を照らしている。守るべきものの暖かさを感じたような、そんな夜だった。