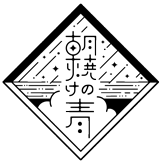いちごのケーキだけ欲しい、とは確かに言ったけど。
目の前に置かれた、いちごがたくさん乗った三段重ねのケーキを前にして、俺は複雑な気持ちで食堂の席に座っていた。
「さあ! 好きなだけ食べていいんだぞ柊!」
紫暮が両手をひろげて俺が食べるのを待っている。俺の前にはフォークとナイフ、それにお皿。どうやらこの三段重ねのケーキを好きなだけ取り分けて好きなだけ食べていいということらしい。
目の前のケーキは紫暮の友達のすごいパティシエさんが作ってくれたというケーキで、真っ白で細かなクリームの装飾がされていて、複雑な切り方をされたいちごや大きさのそろった真っ赤ないちごがあふれそうなほど乗っている。いちごの甘ずっぱさとクリームの甘い香りが幸せな気持ちにしてくれる、とってもおいしそうなケーキだ。きっと三段重ねであったとしてもぺろりと食べられちゃいそうな、魔法みたいなケーキなんだろう。
「いい。みんなで分けよう」
「柊……!! あまりに優しく美しいお前の心に従いたいところだが、今日はお前の誕生日なんだぞ。どうか好きなだけ食べて欲しい」
「そう、いう、ことじゃ、なくて! 多分、食べきれないし、もったいないし、おいしいケーキだったらみんなで分けた方がずっといいし……」
「柊……」
「それに、こういう大きなケーキは……」
月に一回、誰かたちの誕生日を祝うために共同で行われた誕生日会。スポンジにクリームを塗って、缶詰のフルーツを飾って、みんなで作ったケーキをちいさく取り分けてみんなで食べていた。施設は、大切なものはひとり一個までだったけど、大きなものやたくさん入っているものはみんなで分けるものだった。それが当たり前だったし、不満に思ったことなんてなかった。むしろそうするものだと思っていた。みんなで分けると、嬉しかった。
だから、こんなに大きなケーキをひとりで食べていいと言われても、嬉しいと言うよりはむしろ苦しい気持ちの方が大きかった。これは自分でもびっくりした。いつか誰かが「いつか大きなケーキをひとりで食べてみたい!」と言っていたことがある。そういう誰かの夢になりそうなことなのに、ちっとも嬉しいと思えなかった。俺は多分、大きなケーキをひとりで食べてみたいとは思わなかったということなんだろう。その誰かとは違うというだけの話だ。だからこれは、優しさとか、心が美しいとか、そういうことではなくて、考えることの違いという、それだけのことなのだ。
それを、紫暮にどう説明しよう。
「大きな、ケーキは……」
迷って、困っていると、横で腕を組みながら静かに様子を見守っていた巡くんがおもむろに腕をほどいて腰に手をあてた。
「頼城、医学的にもこれだけの量の糖質を一度に摂るのはおすすめしないな。ケーキひと切れに含まれる砂糖の量を知らないわけではないだろう。それがホール三段なんだ。いかにおいしいケーキだったとしてもこれは無茶というものだ」
「むう……だがしかし、日を分ければいいだろう。激しい運動をする若者なのだから、これぐらいはペロリと食べられそうなものだが」
「カロリーの問題じゃないんだよ、頼城。単純に体に障る」
うーん、と唸って口に手を当てて考えだした紫暮は、やがてしぶしぶといった様子で肩を下ろした。
「……柊の、ためにならないというのであれば、そうだな……」
「うん。みんなで分けた方が絶対にいい」
「柊もこう言っているんだ、頼城。ケーキは残念だが、他の祝い方もあるはずだろ?」
「そうだな! 巡の言う通りだ!」
切り替えがめちゃくちゃ早い。
かくしてケーキはみんなで分けて食べることになった。巡くんが一番均等に切れる切り方を教えてくれて、でも綺麗に切り分けられなくてちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったけど。パティシエさんごめんなさい。
でもそのぐちゃぐちゃになっちゃったケーキは本当にすごく美味しかった。スポンジが食べたことないぐらいやわらかくて嗅いだことのない良い匂いがして、クリームが食べたことない味がしていちごがすごくおいしかった。テレビのグルメリポートで「味の大革命だ!」と言っていた人がいたけどそんな感じ。食べたことないケーキだった。とてもおいしかった。
みんながワイワイしゃべりながらその大きなケーキを食べていて、ちょっとほっとした。ケーキを食べるときはこうでなきゃ。大きなケーキをひとりで食べたって、それはちょっと、違うと思うし。
「巡くん、さっきはありがとね」
「ん? ……ああ、なに、事実を言ったまでだ。お前には健康でいてもらわないと困るからな」
ただし、と巡くんがいじわるっぽく笑って矢後さんと口喧嘩してる紫暮をフォークで指した。
「あいつの誕生日を祝うプランを妨害する権利は俺にはないからな、頑張れよ」
「うっ……が、ん、ばる……」
多分、まだたくさん祝ってくれるんだと思う。気持ちはありがたいんだけど、正直に言うとあんまり嬉しいと思いきれない。ちょっと逃げたい。恥ずかしいし、量がすごいし、なんか、重いし……。
「……巡くんもいてね、絶対だよ」
「まぁ、いるぐらいなら構わないぜ。誕生日おめでとう」
「ありがとう……」
革命が起きそうなケーキの続きを食べる。もう帰ってくれないかな。このケーキだけで充分だよ。
向こうから矢後さんとの軽い喧嘩に目処がついたらしい紫暮が笑顔でやってくる。思わず巡くんの方を確認すると目が合った。笑っている。逃げないでいてくれるらしい。よかった。
「柊! ちょっとこちらに来てくれないか!」
まだ長くなりそうな一日を考えてちょっと気が重くなったけど、もう仕方がない。俺はお皿をテーブルに置くと、とぼとぼと紫暮の方に歩いていった。