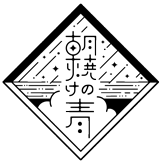春の庭に降りた。さまざまな草花の香りが日光に照らされた土の香りと混ざって鼻腔を通っていく。風もなく、研究員の姿もない、穏やかな庭だった。
冬のしんとした眠りから覚め、春を祝うかのように笑い咲く花たちの間をゆっくりと歩いていく。どの花も美しく、命を喜ぶかのようだった。見事なものだ。
ミモザの木の下にあるベンチにたどり着くと、そこで戸上さんから借りた小説をひらく。分厚いミステリーものだった。とある殺人事件を探偵とその助手が追う。人間関係が複雑に絡み合い、誰もが殺人を犯すに至る理由があるが、誰もがアリバイがある。そして探偵は死者が残したダイイングメッセージに気がつき──そこで以前読み終えていたはずだ。中断していたページから文章を読み進めていく。
今日は非番だが、イーターが出現しない限りは合宿施設で俺の誕生日パーティを予定してくれているらしい。この本は迎えが来るまでの暇つぶしと言える。今回のパーティは始まるまで内容は秘密らしい。頼城は年を重ねるたびにより盛大なパーティを開きたがったから、今回は柊がストッパーになるのだろう。苦労をかける。誕生日プレゼントは人が持てるサイズや重量のものであって欲しいが今年はどうだろう。まぁ、いずれにせよ合宿施設に向かえばわかることだ。
もうじき頼城の車がこちらに来るはずだ。あと三十分もないぐらいだろうか。それなのにわざわざ庭に出てきたのは、今日が誕生日だからだ。
毎年この時期になると身の置き場がないように感じていたあの年のことを思い出す。冬にもいれず、春にも置いていかれ、目的はなく、ただ呼吸ばかりが許されていたあの年の感情を。
学術書が壁一面にある自室も、使用人しかいない大きな家も、研究にしか興味のない研究員が揃っている研究所も、どこにもいることができなかった。薬の研究のために生きてきたのにそれらを禁じられ、なにもできず、なにもする気が起きず、抜けがらだった俺の目に、春を迎え眠りから覚めた明るい植物たちは見ていて希死念慮を抱かせるものだった。
その年を越え、またあたらしい春を迎えたとき、俺は庭が恐ろしかった。自分の家の庭なのに、とても遠いもののように感じていた。けれどそこに咲く植物はなにもしていない。ただ遺伝子に刻まれた命のとおりに生きているだけだ。それを理解するために庭のベンチに座って、草花の香りを嗅いだり、風にそよぐ色形を観察したりした。草花はただ明るかった。そう創られていただけで、なにも誇ったり拒絶したり、ましてや責めたりなどしなかった。
それがわかってからは、きちんと草花を見ておこうという気になったのだ。きっかけが誕生日だったので、おおよそその日に庭に降りてぼんやりと過ごしている。今年は戸上さんに借りた小説があったので、本を読みつつたまに目を草花に向けて眺めたり、沈丁花の香りを嗅いだりして過ごした。
「巡!」
声をかけられて頼城が来たことを知る。顔を上げるとすこし離れて後ろに柊もいる。確か柊をこの庭に通すのは初めてだったはずだ。もの珍しげに辺りをきょろきょろと見渡している。
「さあ行こう。ふっふっふ、今年は特にすごいぞ」
「巡くん先に謝っておく、ごめん」
「ハハ、まぁなんとなく予想はしていたさ」
本を自室に置いていこうか迷って、持っていくことにした。合宿施設の自室に置いておけばいい。最近はあちらに滞在する期間も増えているから不都合はないはずだ。
「止めたんだけど紫暮がどうしてもやりたいって聞かないから……」
「巡の誕生日だからな! 思い出に残る素晴らしい日にするにはあのプランは必要不可欠であって」
「やりすぎなのわかんないの?」
「あー大丈夫だ柊、大抵のことは多分、大丈夫なはずだ、きっと」
広い庭を頼城と柊と共に歩いていく。風の音しかしないはずの庭にふたりの声が重なって賑やかだ。遠くに見える門の外側、停めてある車の脇に藤本の姿も見える。
今日は本当に、祝われ尽くされる覚悟を決めなければならないな。なにが起こるかは秘密ということだから、きっとあっと驚くようなことの連続なのだろう。きっと帰りは遅くなるか合宿施設に泊まることになるだろうから、本を持ってきて正解だったかもしれない。本を読む暇もないほど祝われるのかもしれないが。
沈丁花の香りが遠ざかる。門の外に待機している藤本が頭を下げて車のドアを開ける。波乱の一日の始まりだ。