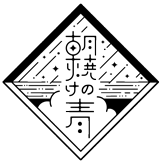年々派手になる誕生日パーティー対策に「今年は極々小規模で」と伝えたところ、なぜか頼城がコックをやることになったらしい。
いわく小規模なパーティといえばホームパーティで、ホームパーティといえばホストが料理をして持てなすことだそうで、それをやってみたかったとかなんとか。
そんな訳で、合宿施設の食堂にあるテーブルの前についた俺の横に、髪を後ろでまとめて給仕服を着た頼城がうやうやしく構えている。
「ホームパーティーじゃなかったのか? なぜ給仕の服を着ている?」
「我が家のコックに料理を教わっている内に持てなしに対する考え方を改めてな。今回はこういったスタイルでやるのも一興かと思った」
「……落ち着かない」
「俺は新鮮で楽しいぞ!」
「ハハ、そいつは何より」
さて、と頼城がキッチンの奥に引っ込み、何かを持って出てきた。銀色の覆いが被さったトレーだ。それを軽やかな足取りで運び、俺の前に優雅な動作で置いた。
「さあ巡、召し上がれ」
カパ、と覆いを開けると、チキンライスの上に綺麗に成形されたオムレツが乗ったものがあった。頼城がそのオムレツの中央にナイフで切れ目を入れていく。オムレツが中央から割れて、目の前に圧倒的な黄色が飛び込んできた。とろりと溶け出した黄身はまるでここ最近の陽気が具現化したかのようだ。ほこほこと湯気を立てながら、周囲に注がれたビーフシチューとチキンライスの香りも鼻に届く。
「巡が一番喜ぶだろうと思ったものを用意した」
「誰が何を喜ぶって? ……ま、まぁいい」
そのオムライスと共に供されたカトラリーケースからスプーンを取り、とろとろの卵に差し込む。卵の下からはオレンジ色のチキンライスが覗いている。周りに注がれているビーフシチューと共にすくって口の中に入れると、シチューと卵の香りが混ざり合って鼻に抜けた。シチューの味も卵の具合も、もちろんチキンライスも申し分ない。
「……うまいな」
「そうだろう?」
弾んだ声で返答するコックは、俺が食べる様子をじっと見つめている。
「……そう見られていると食べづらいんだが?」
「いや何、思いの外嬉しいものだなと思ってな」
横を見ると満面の笑みがそこにあった。
「自分が作ったものを巡が食べる。それがこんなに嬉しいものだとは思わなかった」
「? そういうものか」
「そういうものらしいな」
嬉しいのならば仕方ないのかもしれない。食べるさまなど見て何がそんなに嬉しいのか分からないが、あまり気にしないことにして食べ進めることにした。半熟の卵はとろりとした食感がよく、ライスは鶏肉の旨味がしっかりと染み込んでいる。ひと口ごとにゆっくりと咀嚼していく過程を、頼城は始終にこにこと見つめていた。
やがて皿の上は空になり、俺はスプーンを置く。
「ごちそうさま」
「どういたしまして」
うやうやしく一礼をした頼城が食器を下げていると、柊がそっと声をかけてきた。
「巡くん、食べ終わった?」
「ああ、どうした?」
「ん……あのね、デザートがある」
柊が俺の前にコトリと差し出したのは透明なガラスの器に入ったゼリーだった。薄赤い紅茶と思わしきゼリーに、小さく切られたいちごが沈んでいる。そのつやつやとした表面には絞った生クリームといちごとミントが添えられており、ふわりと紅茶といちごの香りが漂ってきた。
「良くんに聞きながら作った。味見はしたけど……これも多分、大丈夫だと思う」
「ありがとう。大事に食べさせてもらうよ」
ん、と嬉しそうに笑った柊の後ろから戻ってきた頼城がひょっこりと顔を出して、輝かんばかりの笑顔になった。
「おお! 柊の手作りか! 素晴らしい品だな!」
「……あげないからね」
「もちろん。巡の誕生日プレゼントだろう?」
「…………」
柊がムスッとした顔で睨んでいるのを、頼城がきょとんとした顔で見ている。俺は笑いそうになるのを堪えて咳払いで誤魔化した。
「もしかして、他にもあるんじゃないか?」
「ん……巡くんのは特別……だけど」
「なるほどな」
「ん? 何がだ?」
首を傾げる頼城と柊を交互に見る。柊は目を伏せて何かを言おうと頑張って、ごはん、と口にした。
「ごはん、もう食べたの」
「いや、まだだが」
「コック、自分の食事の用意はあるのか?」
「ええ、オムライスが」
「柊の分はあるのか?」
「作ればありますよ」
「じゃあ作ろう。俺も手伝う」
「め、巡くんは座ってて」
結局三人で台所に行き、三人で柊の分のオムライスを作った。頼城は俺の分を作る際に失敗したという、オムライスになり損なったスクランブルエッグを添えたチキンライスを、柊は頼城が成功したとろとろのオムライスを少し複雑そうな表情で食べた。
柊が食後に持ってきたデザートは、紅茶ゼリーの部分がサイダーのゼリーになったものだった。感激した頼城が製品化を提案し、柊が断固として拒否しているのを聞きながらスプーンですくって食べる。いちごの甘酸っぱさと紅茶のさっぱりとした甘さ控えめのゼリーに、なんとなく柊が作ったデザートらしさを感じた。
ゼリーの冷たさに心地よさを感じて、そういえばもう寒くはないのだと気がつく。春なのだ。いちごの粒々とした種を感じながら咀嚼する。ヒーローなんてしておきながら、まだ生きている。うつむくと思い返される出来事があっても、紅茶のゼリーはおいしいのだ。
来年も、こうして食卓を囲めるだろうか。らしくない思いつきは払われないまましばらく頭の片隅に残っていた。