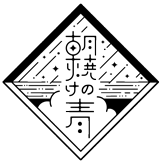春になると巡くんが楽しげにいちごを差し出すようになる。水であらって、へたを取って、ガラスのうつわに盛って、練乳をかけて。そうしてフォークでひとつ刺したものを俺に向ける。
春になると巡くんは冷蔵庫の中にいちごを切らさない。冷蔵庫の中にはいつもいちごと練乳があって、ルビーみたいに光っている。高価なものだからいいのにと言っても、お前のその顔が見たくて買ってると言う。どんな顔をしているのかは、わからない。
今も巡くんはいちごを差し出している。楽しげに。練乳のかかったいちごはいかにも春ですという顔をしてフォークの先で揺れている。
「食べないのか?」
「巡くんが食べていいよ」
「柊のものだ」
「……いつも俺ばっかり」
「いいんだ」
俺は柊を見ているから、と巡くんが言った。
「俺を見てるだけでいいの?」
「そのために買っている」
「いちごみたいにおいしくないよ」
「そんなことないさ」
巡くんはずっと楽しそうだ。よくわからない。
ほら、といちごが揺らされる。練乳がたれてしまいそうだから、あわてて口に含む。あまい、すっぱい、あまい、おいしい。
いちごを食べるとき、口の中から頭のてっぺんまでがじーんとする。多分、感動している。もったいないからゆっくり噛みしめて、味わって、とろけていく果肉を名残惜しみながら飲み込む。
「おいしい」
ため息をつくと巡くんが黙ってふたつ目をフォークに刺した。じゅわ、という音がする。果汁があふれて練乳を洗い流していく。
「ほら」
また目の前にはいちごがある。巡くんはこんなに俺を甘やかしてどうしたいんだろう。毎年のことだから、理由なんてないのかもしれない。おそるおそるフォークの先にかぶりつくと、巡くんの口角がすこし上がった。あ、嬉しい、と思う。巡くんが嬉しそうだと、俺も嬉しい。
いちごがおいしくて、巡くんも嬉しそうだなんて、こんないいことはそうそうない。春はいい。とてもいい。ゆっくりゆっくり春のかたまりを味わう。
「やっぱり巡くんも食べた方がいい」
「全部柊のものだぞ?」
多分巡くんは自分から食べない。だから俺は巡くんにキスをした。
「いちごの味、わかる?」
「分からないな」
巡くんが自分からキスをして俺の唇を舐めた。
「こうでもしないと」
「おいしい?」
「とても」
よかった。巡くんが笑う。もうそれだけでいいのに、いちごなんてくれて、甘やかして、度がすぎると思う。でも嬉しいから、また来年の春も、再来年の春も、甘やかしてくれたら嬉しいなと思った。