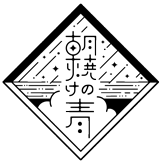柊は昔っからかくれんぼが得意だった。人が寄りつかなさそうなところを見つけるのが得意なのだ。それで終わった頃にみんなでもう降参だ、と言って回るとひょっこり出てきて、控えめに笑う。俺の勝ち。あんまりそんなことが続くから、俺は柊が隠れそうな場所をなんとなく覚えてしまって、だから頼城さんや伊勢崎が探し回っている中でもこっそり見つけることができてしまう。
「柊」
暖房のない空き教室の中、後ろの扉を背にして体育座りをしていた柊はこちらに視線を向けると、ほんの少しだけこわばった表情で良くん、と返した。
「大丈夫、見つかってない」
そう言うと少しだけほっとしたような顔に戻る。柊のそばに行って横に座ったけど、体温を感じない。きっと冷えているのだろう。ここ寒くねえ? と言うと、少しだけ、と手をすり合わせる仕草をする。うん、やっぱ早めに来てよかった。
「今から飯食いにいかねぇ? 人のいない穴場知ってんだ」
綺麗で小さい食堂でさ、デザートに確かいちごのケーキもあったから、俺の奢りで。行こうぜ、もうじき昼だし。そう言って手をつなぐ。柊の手は冷たくて、あまり長くここにいてはいけないと思った。柊は少し悩んでいたけど、俺が先に立って手を少し引っ張ると、ゆっくり立ち上がって歩き出した。見つからないように、人の気配を探して避けていくのはふたりとも得意だったから何事もなく外に出られた。
外に出てしばらく歩くと、目的の店につく。木の板で作られた外観は比較的時間の経過を感じる風合いだけど、よく手入れがされていて綺麗だった。入り口にいくつかある観葉植物もよく育っていて、青々と葉を伸ばしている。木でできた看板には白いペンキで外国語の店名とコーヒーカップが描かれていて、時間の経過で少し色あせていた。
ドアを開けると、からんからんとベルが鳴る。よく磨かれた木でできた店内は昼前ということもあり人はまばらで、一番奥の向かい合わせのテーブルに座ることができた。洋食のラインナップが並んでいるメニューの中から、柊はオムライスを選んだ。俺も適当に腹に溜まりそうなものを選んで注文する。静かな声で話す店員は伝票に注文を書きつけると会釈をして厨房へと戻っていった。
「……ありがとう、良くん。今日は朝から逃げまわってて、ご飯食べれてなかったから、お腹すいてた」
「朝からか……頼城さんももう少し控えめにできれば……いや、無理だなあの人」
高らかに合宿施設に響く「柊!」は今日何回も聞いた。伊勢崎も便乗していたから逃げ回るのにさぞ忙しかっただろう。柊はコップに入った冷たい水を少し飲んで細く長く息をはいた。
「頼城さんも悪い人じゃないんだけどなぁ」
「……分かってる、けど、無理なものは無理」
「柊が無理する必要はねぇけど」
頼城さんが柊のことを大切に思っていて、生まれた日を祝いたい気持ちでいるのは分かってる。でも実際、柊は冷えてしまっているしお腹を空かせている。うまいことどうにかなればいいんだけどと思いながら俺もお冷やを飲んだ。冷たい水が首の中を通っていくのが分かる。柊は氷水みたいに純粋だ。頼城さんは暖かい人だけど、氷水は温めたら別のものになってしまう。難しいよなぁと思っていると、お待たせしましたと言って黄色のオムライスが運ばれてきた。俺の前にも注文したものが置かれる。
「柊、オムライス好きだっけ」
「ううん、どっちかっていうと、巡くんが好き。最近よく見かけてたから、食べたくなって」
そっか、カチャカチャとカトラリーを取っていただきますと手を合わせる。氷水だって、ただの氷水のままではいないのかもしれない。例えば、黄色い、そうだな、しぼりレモンの入った氷水になったり。俺はアイスの天ぷらを思い出しながら、それなら温かい氷水だって存在するかもしれないと空想した。世の中は広いから、もしかしたらあるのかもしれない。
そうやって食べていると、スマホがメッセージの着信を告げた。斎樹さんからだった。『柊を見なかったか?』……どっちの味方だろう。俺は悩んで、結局柊に伝えた。
「……」
柊も同じことを考えているみたいだった。悩んでいる間にもスプーンは進む。オムライスは減っていく。
「観念して祝われるっていうのもひとつの手だぜ、こうなったら」
「……分かってる」
そうこうしている間にオムライスはなくなってしまった。さっき見たメニューに載ってた、いちごのショートケーキの文字を思い出す。
「ケーキ頼む?」
「……ううん、いい。多分、帰ったら、すごく大きいのがあるから」
「そっか」
お冷やをあおると、来た時よりも冷たさがやわらいでいた。それでも氷は浮かんでいる。よかった、と俺は嬉しくなった。
「うっし、帰るか」
「うん。……ご飯、ありがとう」
「どういたしまして」
柊の金色の目がちらりと見えた。頼城さんと斎樹さんはこの世にないものを生み出せる人たちだから、あるいはきっとできるのかもしれない。アイスの天ぷらみたいに。柊の隣に並んで歩くと暖かかったから、俺は安心して合宿施設の道を帰ることができた。