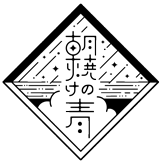「夢を見たんだ」
隣を歩く頼城が唐突に言った。
雪が周りの音を吸収して静かな夜、電灯の下、濃い影を作った頼城が足元の雪を鳴らす。
「どんな夢だ?」
「巡が生まれる夢だ」
分娩室の前で、巡が生まれるのを今か今かと待っている夢だ。一分一秒が長く感じて、ずっと喉が苦しくて、じっと座っていられなかった。待合の椅子の上とドアの前を行ったり来たりしていて、ついに産声を聞いた時にはいてもたってもいられず許可もないのにドアを開いて飛び込んだ。生まれたばかりの巡はすぐに看護師に取り上げられて産湯につかり、なぜか俺の元に連れてこられた。生まれたばかりの巡はとても小さくて、恐怖を感じるほど柔らかくて、泣きそうなほど暖かかった。
「それは、夢だな、確かに」
俺は人の腹から生まれてはいない。無機質な厚いガラスケースの中に溜められた培養液の中で育ち、一定の大きさになった頃に取り出された、それが俺の誕生の仕方だ。そこに人の温度はない。
「生まれたばかりの巡を抱いたとき、夢の中で母性を理解したんだ」
「母性」
あれは守るべきものだと瞬時に理解した。愛すべき対象だと。そう言った頼城の表情は俺からの視点ではよく見えない。だが声の調子から判断するに、ろくでもない感慨に浸っているに違いない。
「言っておくが俺はお前に母性なんぞ求めてないからな」
「ああ、分かっているとも。俺はお前を信頼という形で愛している」
だから、巡、お前を信じている。そう言った頼城は横から消えた。
その時に理解した。頼城は死んだのだと。俺を取りあげてそれから死んだのだと。戦いの中で、敵の攻撃で、俺が守る間もなく死んだ。そういえば先日、葬式を挙げたのだった。盛大な葬式だった。多くの参拝客の中、俺は奴の死を悲しむただのひとりの人間で、特別なことはなにもなく、式はつつがなく終わった。
なぜ忘れていたんだろう。今日は、頼城の死に考慮して俺は非番だった。どこに出かけていたのかは思い出せない。横にいた頼城はもういない。
雪の降る道はただただ静かで、定点的に存在する電灯が道を照らしている。音はなく、俺は一人で、これから来る春が心底怖かった。
*
「そういう夢を見た、と」
目の前でスクランブルエッグを乗せたトーストをかじっている頼城は当たり前のように生きていて、口の端についた半熟の卵をぺろりとおいしそうに舐めとった。
「きっと疲れていたのだろう。俺は詳しくないが生死に関わる夢は吉夢だともいう」
「疲れていたんだろうな。やたらとリアリティがあったんだ、それで少し混乱した」
「ああ、俺もまれにある」
「例えば?」
「巡がまだ生きている夢を見る」
巡はもう死んでしまったのに。あの日、俺が間に合わなかったから。もう少し早く家を出ていれば巡は薬を飲まずに済んだのに。
そういう頼城の顔が一瞬かげって、胸元のカプセル式のアクセサリーが揺れた。
「それは?」
「巡だ」
よく見れば頼城のトーストを握る手の指先にはブルーブラックのインキがついていて、先程までペンを握っていたんだということが分かった。お前、そういうことは効率重視でデジタル派じゃなかったか。
「まぁ、そういうことは往々にしてあることだ。あまり気にするな。疲れているなら今日はゆっくり休むといい」
*
「…………」
目を開けると、そこは家のベッドの上だった。時計を見るとアラームが鳴る一分前の表示で、ぼうっとしながらアラームが鳴る前に動作を止める。これは夢か? 現実か? よく分からない。ぼんやりした頭のまま洗面所に行き、顔を洗う。夢の内容ははっきりとしていたのに、起きてしまえば段々と内容を思い出せなくなっていく。確か頼城が出てきた、誰かが死ぬ夢を見たような気が、する、そうだ、俺は今日、確か、死のうと思っていたんだった。自室の引き出しにしまった数錠の錠剤のことを思い出す。
顔を上げた鏡の中の自分の瞳の色は黄金ではなかった。