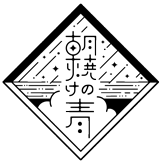※ラクロワが三人婚してる前提の話です
今夜はどうやら流星群が流れるらしいとニュースキャスターが言っていたから、少し外でも歩こうか、と上着とマフラーを引っ掛けて外に出たのが数分前。流石にそんなに見えないんじゃないか、だって流れ星だ。と思っていたが、近所の公園のベンチに座ってぼうっと上を見ているだけで、降り始めの雨のようにぽつりぽつりと流れ星が落ちてくるのが見えた。
きれいだ、と柊が言い、ああ美しいな、と頼城が続く。俺はと言えば頭に浮かんでくるのは太陽系惑星の黄道図、流星群の仕組み、しぶんぎ座にまつわるいくつかの論文の切れ端、そんなもので、素直な感想を口にするには少しばかりノイズが多すぎた。けれど、そんな知識のノイズにまみれていても澄みきった空に流れる光の尾は美しく、ああ、よく燃えていると、それだけをやっと口にする。
一月四日、新年が始まって間もない今、しぶんぎ座流星群が一番近くで観測できる日だ。風はなく、澄み切った空が清々しい。頬は冷たく凍てつきそうで、マフラーのやわらかささえも感じ取れるか怪しいところだった。けれどもそれは少しも嫌な寒さではなく、新年の消毒液をまぶしたような清潔さをともない、皮膚の薄い耳や足の裾から入り込み、己が浄化されるような心地だった。そんな空気の中、次々と降ってくる流れ星はどこか夢のようで、ずっと空を見上げていたこの視線を下ろしたら近所の公園ではなく、どこか別の土地にワープしていて、例えば砂漠の真ん中にいるのではという妄想を連れてくる。きっとそれは空を見続けたことで三半規管が平衡性を少しばかり失って、気管が圧迫されたことによる軽い酸欠で、それらが合わさったことによるものだろうと天地が分からなくなってきた頭で考える。
「以前もこのように三人で空を見上げたことがなかっただろうか」
急に頼城が言い出して、柊とふたりで顔を起こして見つめ合う。
「いや、俺が覚えている限りないが」
「なに、前世の話?」
「今生であるはずだが」
頼城は空を見たまま考え続けている。その様子を見て俺ももう一度空を見上げた。スッと尾を引く大きな流れ星がひとつ、流れていく。続けてふたつ、みっつ。三つの流れ星はそれぞれ時差をおきながら燃えて、消えていった。それを見ていた頼城は、ああ、と合点が言ったように声を上げた。
「手術の時に見た夢だ」
「手術? ミュータント化手術を受けた時か?」
「そうだ、その時にこうして三人で流れ星を見る夢を見た」
「正夢ってやつ?」
「かもしれないな」
きっとそれは麻酔薬が見せた幻で、今の俺たちとはなんの関係もないのだろう。三年限りのヒーローのために金眼の光を灯した俺たちを、流れ星に見立てた頼城の精神が見せた幻だ。けれど頼城は笑った。
「家族ができると思っていたのかもしれない、もうその時に」
頼城は俺たちのことを家族だと呼ぶ。俺も柊も、まだそれに少し慣れないでいる。ふたりとも、自分の中にある「家族」の定義があやふやだったからだ。あたたかで、守られていて、幸せで、連綿と続くはずの「家族」はふたりして実感を伴わず、想像上の生き物のように伝説になっていた。それの襟首を掴んで眼前に突きつけてきたのが頼城だ。それを受け取るか受け取らないかは別として、頼城は惜しみなくそれを積み上げた。それを受け取ってしまったのが運の尽きとでも言うべきか、なぜか三人揃って同じ家に住んでいる。それを家族だと認識できる日が来るのかどうかは分からないが、少しずつ言わんとしていることが分かるようにはなってきた、と思う。
「運命ってこと?」
柊が空を見ながら尋ねた。俺たちがヒーローになって、使って、守ったものの名前だ。イーターと戦った日々が傷のうずきを伴って再生される。俺たちがヒーローになることすらも運命の一部だったのなら、こうして三人でいることも運命なのかもしれない。
「運命が切り拓いた先の結果としてあるものならば、あるいは」
自らを被験者一号として捧げた男はそう言った。
「切り拓くための手術で受けた麻酔が見せた幻が今と重なるのであれば、それはきっと頼城の言うところの運命だろう」
毎年観測される流星群のように金の光が重なったタイミングが今なのだ。これからもこうして薄紙を束ねるようにしていけば、この共同体を家族として認識できる日が来るかもしれない。きっと来るその日に確信を持ってしまった。燃え尽きたあとの流れ星はどこに行くのだろう。暖かなところへ行けるといい。帰ったらハーブティーでも淹れて、三人で揃って眠ろう。また巡る一年のために。