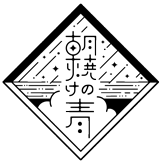俺の母は機械でもある。産みの母のことだ。
俺の育ての母は受精卵を培養液に入れ、大きな試験管で俺を育てそこから取り出した。SF映画なんかでよくある、液体の入った円柱型の装置があるだろう。あれに近い。そしてその装置は、まだ家の地下に資料として保管されている。もう動くことはないだろうが。
久し振りに地下室の扉を開けると、薄暗い部屋の中に母はいた。埃避け用の白い布を被った円柱型の装置は、中身の液体を抜かれて綺麗に磨かれている。ひたりと手で触れるとガラス製の円柱はしんと冷たく、やがて俺の熱で温まって同じ温度になった。
少しだけ、この中に入っていた時のことを覚えている。薄暗い空間の中、何かがピカピカと光っていて(恐らくモニターだろう)、動く何かがいるような記憶だ。後から聞いた話によると、何度か部下の研究員を連れて俺の経過観察会を行なっていたというから、その時の光景だろう。円柱の中で成長する遺伝子操作を行った胎児をどんな気持ちで見つめていたんだろう。恐らくはただの実験動物と変わりない感覚だったに違いない。ぞっとしない話だ。
俺は円柱に背をもたれて地面に座り込んだ。そのまま後頭部を少し強く円柱にぶつけると、少しだけ埃っぽくて薬品の匂いのする空気がゴトンと揺れた。落ち着く匂いだと思う。幼い頃から親しんだ匂いだ。この環境を憎んだことなどなかった。幼い頃から実験と勉強に明け暮れた俺を憐れむ奴もいたが、別に苦痛に感じたことなどなかったのだからそれはお門違いという奴だ。楽しい、ということもなかったが、そうだな、向いていたのだ。向いているからいつまでやっていても飽きないし、成果を出せる。それはとても幸福なことだと思っていた。頼城にあの言葉を言われるまでは。
頼城曰く、俺は向いていないことをやるようになってからよく怒ったり笑ったりするようになったのだそうだ。そういった自覚はあるが、それ以前はそんなに表情がなかっただろうか、俺は。そう考えてから、俺は俺自身のことには割と無関心かもしれないなと思い至る。自分が笑っていたかどうかすら把握できていないのだから。
そうしたとりとめのない事をつらつらと考えて、戻ろうと思った。ここに来た理由も特にはない。ただ、たまに来たくなるのだ。この中に入っていた時の記憶をより強く思い出せる気がするから。成長するに伴って、胎児の頃の記憶は薄れていくようだった。それを繋ぎ止めるためにこうしてたまにここに来る。何故か、忘れてしまいたくないと思うからだ。それは貴重性のためかもしれないし、そうじゃないかもしれない。自分でもよく分からない感情の動きだった。
ガラス製の円柱に埃除けの布をかけ直す。触った時にうっすらとついた指紋をその布で擦り落として、最後にもう一度中身を見直した。栄養素が滞りなく運ばれるチューブの出入り口、中の液体が漏れないような分厚いガラス。それらを支える金属の土台。およそ母と呼ぶにはふさわしくない無骨な作りのこれがなければ、俺は生まれてこなかったのだ。
布をしっかりと掛けてから、出入り口の取っ手に手をかける。キィと軽い物音を立てて開いたドアの向こうは明るく、初夏の瑞々しい眩しさで今日も暑くなりそうだった。薄暗い物置の中の円柱を視界に入れながらドアを閉める。カチャリと閉まったドアの向こうからは何も生気がない。鍵を閉め、静かな廊下を歩いて鍵置きのある場所へと向かう。
墓参り、そんな単語が頭をよぎった。