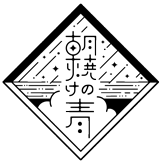頼城紫暮という人間は、星のようなやつだった。
沢山の書籍と論文に囲まれて実験に明け暮れていた幼少期の俺に、何度も何度も一方的に会いに来ては土産を渡してきたのが頼城だった。
俺の両親の知人に頼城の親がいて、歳が近い息子がいるからと会わされたのがそもそもの始まりだった。何かのパーティのことだったと思う。その年齢の子供は俺たちふたりだけで、大人たちが話している間、会場の窓際、カーテンがゆらめくテラスで星あかりの下ふたりで話したのだった。
「ニュースで見たんだ。君は最年少で医学博士の資格を取ったんだろう? すごいな!」
「大したことじゃない。人を治せる医師になったわけではなく、ただの資格取得でしかない。俺がなすべきことはこの先だ」
もう何度も繰り返された話題だった。ニュースキャスターにコメントを求められたこともある。その度に繰り返す。なすべきことはこの先にある。なぜなら俺はこの資格取得の先にあることを求められて生まれた命だからだ。これはまだ始まりでしかない。
それを伝えると大抵の人は驚き、感心し、立派ですねなどと言う。そのように設計された人間なのだからそうなって当たり前だ。立派なんてものじゃない。ただただ設計された通りに機能した結果がこうなっただけだ。俺がこう返答することすら、きっと設計通りなのだ。
頼城はそれを聞いて顔を輝かせた。
「そうとも! その先にある! なすべきことはこれからもっともっとある! 俺もそうなんだ! これからが楽しみだな!」
言われた言葉が意外でうまく飲み込めなかった。自分もそうだと言っている。そしてそれが楽しみだと。
「……君も、ええと頼城くんも、その、デザイナーベビーなのか?」
「紫暮で構わない。いいや、俺はデザイナーベビーではないが、使命を持っていてね。世界をより良くするという使命だ」
「……頼城、と呼ばせていただこう。その、世界をより良くする使命、というのは?」
「今、東成都はヒーローに守られている。しかしヒーローは生まれ持った素質に左右される。俺が目指すのは、誰しもが生まれ持った血性値に関わらずヒーローを目指せる世界だ」
頼城はその青く澄んだ瞳で語った。話を聞くと、どうやらそれは夢物語ではなく医学的エビデンスのある話のようだった。今はまだ実験段階だが、いつか必ず実現してみせると頼城は言った。
「巡くんのなすべきこととはどんなことなんだ?」
「巡で構わない。俺は……新たな薬を生み出し、改良し、医学の発展に貢献するために生まれた。だから成さなければならない。薬の開発を、病の根絶を」
「素晴らしいな。巡が新しい薬を開発する日が楽しみだな!」
満面の笑みで手にしたグラスを傾けられる。促されるがままに自分の持っているグラスを合わせると、カチンと硬質な音がした。頼城は楽しげに自分のグラスの液体を飲み下す。俺はゆらゆらと揺れる手の中の水面を見つめた。シャンデリアの明かりが小さな波にちらちらと輝いている。星のようなそれを、俺は飲み干す気になれなかった。
「悪いが楽しみだと思ったことはない。これは義務だ。責任と言い換えてもいい」
「責任? なんの責任だ」
「そう設計されて生み出された以上、役割を果たさなければならない。そこに楽しみや達成感など必要ない。生まれた責任を持って俺はこれからなすべきことをなす」
「……そうか」
頼城が微笑んだ。その笑みがどこか無表情に近いと思ったのは、次の瞬間いいことを思いついたとひかるような顔で笑った顔を見たからだった。
「来週、予定は空いているか? 遊びに行っても構わないか?」
「構わないが……大したもてなしはできないぞ」
「構わないさ。何、時間はそんなに取らせない」
その言葉の通り、頼城はほんの短時間だが会いに来て、風のように去っていった。そしてそれを何度も繰り返した。手土産に花を持って。
最初の訪問の時はガーベラだった。色とりどりのガーベラは使用人によって青く透明な花器に生けられ、俺の部屋に飾られた。本と机と椅子しかない部屋に花があるのはなんだか落ち着かなかったが、毎度訪問の度に花を持ってくるのでやがて慣れていった。
初めて会ったのが春先だったので、ガーベラから始まりラナンキュラス、チューリップ、ルピナス、鈴蘭、バラ、百合、ラベンダー等々、俺の部屋には花が絶えることがなくなった。紙の匂いが立ち込めるばかりだった部屋の中に、いつも花の匂いがするようになった。
頼城と会ってからというもの、切り花は案外寿命が短いことを知った。頼城は持ってきた花が枯れる前にまた花を持って会いに来た。春も夏も秋も冬も、いくどもいくどもそれを繰り返すので、こいつの愛情表現はいささか過剰すぎないかと呆れたことがある。
いつか、頼城に聞いたことがある。なぜ花を持ってくるのかと。
「綺麗なものを贈りたいんだ、巡に」
「なぜだ? 俺にそんなことをしても無駄だろうに」
「使命を果たすことのみを目指す生命は美しいだろう。それにふさわしいと思ったんだ、花が」
こいつの価値観はよく分からなかった。俺のことを美しいと言う。花がふさわしいと言う。難しい式だ。個人の価値観の違い、だと思う。よく分からないながらも受け取る花は美しく、香はかぐわしく、みな等しく枯れていった。
結果として、俺と花は等しかった。すなわち枯れる運命にあった。いや、それは花に失礼かもしれない。花は美しく咲くための品種改良を重ねた結果の成功であり、俺は品種改良を重ねた上でできた失敗作だったからだ。
「巡……お前は失敗作だな」
そう言われたとき、死んでしまいたいと思った。死ぬべきだと思った。世の中に自分のようなものが存在してはいけないという気持ちで脳の回路が焼き切れそうで、死にたくて、もうそのことしか考えられなくなった。
白衣を脱ぎ、研究所を離れた俺はそれでも数日考えた。考えても考えても死ぬことがふさわしいと思えたので、死ぬことにした。
死ぬ方法は色々と考えたが、毒を調合してそれを飲むことにした。人の命を救う薬を生み出すために作られた俺が人を殺す薬を生み、飲んで死ぬことは失敗作である自分にふさわしいと思った。
毒を調合し、遺品を整理し、遺書を書いている時に頼城がやってきた。俺は遺書を隠し、頼城を迎えた。
「やあ巡! 調子はどうだ?」
季節は巡って春を迎えていた。今日の花はガーベラ。頼城が最初にうちを訪れた際に持ってきた花だ。希望、常に前進。ガーベラの花言葉だ。今の状況にとんでもなく不釣り合いで笑いが出る。
「巡?」
「ああいや、なんでもない。俺に似合いの花だと思ってな」
「巡がそういうことを言うのは珍しいな」
頼城が不思議そうに笑いながら花を手渡した。新鮮な花の香りだ。色とりどりのガーベラは瑞々しい花弁を八方に伸ばして笑うように咲いている。
何が似合いの花だ。花はこんなにもあかるく美しいのに、俺に似合うわけなどない。
「ひどい顔だ、なにかあったのか」
頼城が眉をひそめて顔を覗き込んでくる。まるで自分が苦しんでいるかのようだ。青い双眸が俺を射抜く。やめろ、やめてくれ。そんな顔で俺を見るな。
「巡……」
「もう、来るのはやめてくれないか」
喉がひりつく。嗚咽が出そうになるのをこらえて目をそらした。頼城がじっと俺を見ているのが分かる。こいつは今どんな顔で、この間違いだらけの俺を見ているのか。想像したら泣きそうになった。
「俺はもう、」
死ぬんだから、と告げる。サッと耳元で血液が引いた音がした。言ってしまった。後戻りはできない。今すぐに死にたくなる。体の芯が冷たくなって、胃が痛む。もう帰ってくれ、と言おうとしたがその言葉は遮られた。頼城が俺を息ができない強さで抱きしめたからだ。離せ、と口にした声はかすれて耳に届かなかった。頼城の背を何度も叩く。
「そんなことはさせない」
ぎゅう、と頼城の腕が俺の胴体を絞っていく。頼城の体は熱かった。人の体はこんなにも熱いものなのかと頭のどこかで冷静に驚く自分がいた。人に抱きしめられたのはそれが初めてだった。たった数度の体温の違いが、こんなにも冷え切った芯を温めるものなのかと衝撃を受けたまま、死ぬことに対しての執着を失わないよう自分を律する必要があった。そうでもしなければ、ほだされてしまうと思ったからだ。この熱さに温められることを許せるような、そんな正しい生命ではないのに。
「俺は失敗作だったんだ、だから死ぬべきだ」
「……失敗作?」
「ああ、俺は、失敗作、だ。そう言われたんだ、両親に」
他でもない、俺を作った創造主に。とてつもなくみじめだった。
両親は以前、俺になるはずだった沢山のサンプルを見せてくれた。といってもすべて画像で、元のサンプルはすべて廃棄されていたのだが。色々と遺伝子操作をする中で、俺のパターンが一番優れていたのだと語った。数学的思考と記憶力に優れて、音楽家に共通する遺伝子配列の、沢山のテストの末に選ばれたのが俺だった。沢山の、本当に沢山のサンプルの中から俺を選んだ。だから、その時点では恐らく間違っていなかったのだ。
問題は、俺の成長過程の中にあった。俺が両親の選択を台無しにしたのだ。ならば、俺は自分自身を廃棄しなければいけない。
「だから、頼城、俺は、」
「巡、お前がお前を殺すというのなら、俺がその命を預かろう」
「預か、る?」
「お前を殺すかもしれない人間に、お前の命は任せられない。だから、俺がお前の命を預かる」
「……預かって、どうしようというんだ」
失敗作でしかない俺の命を預かったところで、こいつに利益なんてない。不完全な俺を生かす理由が分からなかった。
「お前の命の使い方は、いくらでもある」
頼城が俺をゆっくりと解放した。青い双眸の光がまっすぐに目をつらぬく。それがレーザーのように網膜に焼きついてチカチカと星が舞った。
「巡、お前は自分の持つ才能から離れろ。そして、もっと自分に『向いてないこと』をするべきだ」
「向いていない、こと……?」
「そう、例えば……」
ヒーローだ、と頼城が言った。ヒーロー。体を張って人のためにイーターを倒し、人を助ける少年たち。なるほど、それは確かに向いていない。
「……人体実験か、いいだろう。好きに使ってくれ」
「ああ、ちなみに被験者一号は俺が務めるから安心してくれて構わない」
「そこは俺がすべきところだろう」
「いいや、栄えある第一号を譲る気はないな」
どこか得意げに言い切ってみせた頼城はそれを本気で言っているようだった。折角自由に使える命がここにあるというのに。しかし頼城はこの技術を心の底から愛している人間だったから、最初にその技術を身に受けたいと考えるのも順当なことかもしれなかった。
「巡には被験者第二号としてヒーローになってもらう」
その決定を、肯定以外を持って迎える用意は俺になかった。
それから、ヒーローになるための準備が始まった。今までやったことのない身体を使ったトレーニングは想像を絶する過酷さで、今まで運動などろくにしたことがない俺は何度も吐いてそれでも水を飲み、身体を動かし、終わったあとは気絶するように眠ることを繰り返した。
正直死んだ方がマシだったのでは? と思う日々の中でも頼城はやっぱり定期的に会いにきて、ゲロにまみれた俺に花を渡しては笑顔で「調子はどうだ?」などと言い出すので殴ってやろうかと思ったこともある。
それでも何ヶ月かトレーニングを続けていくうちに身体が慣れてきて、吐くことも気絶するように眠ることも減ってきた。余裕が出てきたので、一般人をヒーローにする研究についても首を突っ込んだ。頼城は俺がまた研究に関わることを内心心配していたようだが、特に問題を起こすこともなく上手くやれた、と思う。そのはずだ。
ただ確認を繰り返しする癖がついてしまって、頼城がヒーロー化手術……ミュータント化手術を受けることが決定してからも、どこかで間違いが起きていないか執拗に確認を続け、頼城からやりすぎだと苦言を受けたほどだ。
それでも確認がしたかった。頼城の手術がもし万が一失敗したらと思うと、恐ろしかった。こいつを科学の礎なんぞにしてたまるかと何度も何度も繰り返し検証して、結果を確認した。
そして手術は行われ、俺は手術室前でただただ祈ることしかできなかった。あの時ほどいかに自分が無力な存在かと痛感したことはなかった。手術室前の長椅子に座ったり立ったり「手術中」のランプがいつ消えるか度々見上げ、うろうろとさまよった数時間後、手術中のランプが消え、執刀を行った先生が出てきた。
「大丈夫ですよ、手術は無事成功しました」
その言葉を聞いた俺は、心底ほっとしてへたり込みそうになった。
「しばらくは無菌病室で経過を見ることになります、手術室に入ることはすみませんが控えていただいて……」
「はい……分かっています」
先生が会釈してその場を離れ、しばらくしてストレッチャーに乗せられた、麻酔で眠っている頼城が運ばれてきたのをぼんやりとただ見守った。
無菌病室は基本的に家族の入室しか許可されていない。だから、俺は頼城がおおよそ回復し、通常病室に入るまでかなりやきもきしながら待っていた。毎日のトレーニングをしながら、食事をしながら、寝る前ですら、頼城からの連絡をずっと待っていた。そのような感じだったので、藤本さんから連絡を受け、飛ぶように病室に向かった先でのんきにパソコンで仕事をしながら「やあ、元気か巡!」と迎えられた時にはがっくりと肩を落としたものだった。
「……それは、俺の、台詞だろう」
「どうしたそんなに憔悴して……むう、そうだった、まだベッドから自力で起き上がれないんだ、すまないがこちらに来てくれ」
はぁ、と思わずため息をつき、頼城の元へ向かってすぐ変化に気づいた。すでにラットなどを使用した実験で承知していたことだった。けれど忘れていた。深く青い、星が浮かぶような瞳が片方、黄金へと変わっている。思わず立ち尽くしていると、頼城の顔に満面の笑みが浮かべられた。
「美しいだろう? ヒーローを志す者の意志の色だ」
「……ハハ、ああ、そうだな」
美しい、か。確かにそうだ。俺がそれを副作用と捉えたにすぎず、そうと表現しえなかっただけで、この瞳は確かに美しい。こいつはそういう、世の中の綺麗なものに目を向けるのが得意なのだ。
近づいて前髪をそっとかき分ける。病室内に差し込むしらじらとした日光に照らされて、金と青の瞳は凛と芯から光っていた。
「……綺麗なもんだな」
そううっかり声に出してしまったので、頼城がぱあっと笑って、しまったと思ったのも束の間、笑い声と共に抱きしめられて焦ってしまいぽこすか殴っていたら頼城の傷が開いて痛がったので、慌ててナースコールを押して二人で婦長に怒られその日の面会時間は終了した。
それから通える日は毎日頼城の病室へと通った。手土産に花を持って。といってもどんな花がいいのかまるで分からなかったので、近場の花屋の店員に勧められたものを買っていく、という有様だったが。
コスモス、ダリア、クジャクソウ、バラ、セージ、カンナ、秋口だったのでそんな感じの花を、いつも携えて見舞いに行った。病室は個室だったので、こういう花がかさばらなくてよかった。俺以外の見舞い客からも花が届くので、病室は花であふれていた。その花瓶の水を、たまに俺が換えていた。ひとつひとつ頼城に宛てた花の水を換えて持っていくと、ありがとうとかすまないなとか、言葉が返ってくる。それを気にするなと一蹴して頼城の周りに置いていく。
「ああ、やっぱりお前の方がよっぽど似合う」
「なんの話だ?」
「花の話だ」
最後の花瓶をことりと置いて数歩後ろに下がる。病室特有の白さや病院着といったものは気になるが、花と頼城はとても絵になった。秋口の花に囲まれた頼城はこちらを見て微笑んでいる。きらきらと金と青の目が光る。
「覚えてくれていたのか。ああでも、今の巡に似合う花は昔とまた違うだろうな」
「どういう意味だ」
「目がひかっている、意志ある瞳だ。もっと、そう、色の濃い大輪の花が似合うだろう、昔よりは」
まぁ俺の好みの話だが、と言われてしまっては返す言葉もない。意志ある瞳、そうだろうか。
「……お前と比べると、そんな気がしない」
「ふふ、そうか? いい目をしているよ。同じ金の瞳になれるのが誇らしい」
近くに寄り、手近な椅子に座ると頼城が俺の前髪をかき分けて目を見つめた。俺も頼城の目を見つめる。頼城は穏やかな目元をしていた。鮮やかな金と青の瞳のコントラストが夜空か宝石を想起させる。およそ人体のパーツと思えないほどそれは美しかった。俺の目元を頼城の指がゆっくりとなでていって、やがて、ふ、と口元がゆるめられた。
「そのうち揃っては見られなくなるかと思うと惜しいな。好きなんだ、巡の目の色が」
「片方は残るんだ。好きなだけ見ればいい」
「ふふ、ああ、そうしよう」
だが結果として俺の目は両方とも金に変わり、二度と生来の色を見ることが叶わなくなった。頼城はそれをひどく惜しんで、ふたりで写っている写真をA0サイズに引き伸ばそうとしたが俺が説得してなんとか止めた。
その代わり、と言って頼城は一般的な写真立てに収まるサイズでその写真を印刷し、自室の机上に飾ったようだった。それはなんだかむず痒く、気恥ずかしい気持ちにさせられることだったが、頼城が「覚えておきたいんだ、巡の色を」と言うので好きにさせた。
退院してすぐにALIVEから連絡があり、武器を選ぶことになった。ALIVEに赴くと武器適性を見るテストのようなものを受けさせられ、結果は術式。一番向いていないのは重式だった。当たり前だ、この身長で大物を振り回すのは無理がある。
「テストを受けてくれてどうもありがとう。僕は神ヶ原といいます。ALIVEで武器や戦闘服なんかの開発担当をしています。どうぞよろしくね。えーとそれで武器の説明なんだけど、術式は主に後方から攻撃する武器種になります。この辺りは知ってるかもね。それで具体的な武器の形なんだけれど……」
職員から武器の説明を受けサンプル武器を装着し、シミュレーターで敵を実際に撃破していく。術式は、基本的には点と点をつなぎそれを線や面として扱う武器種らしい。崖縁のように技術参入があればまた違うのだそうだ。ラ・クロワはそういった面での技術参入はないだろうから従来通りの運用方法となるだろう。
「頼城はどんな武器を選んだんだ? 相性を見ておきたい」
「頼城くんだね。彼はガンサーベルを選んでいるよ。銃剣だね。前衛にも後衛にもなれる武器でひとりで戦うには適している。武器種で言うと迅式だね。ただ前衛か後衛、どっちかのサポートがあった方が安定するだろうね」
術式は基本的には後衛だ。ということは頼城に前衛を任せることになる。本来であれば重式が担う部分だ。重式は攻撃を受け止めるために頑丈で重い武器を扱うが、頼城のガンサーベルでは少々難しいだろう。
「頼城くんのガンサーベルのことを心配しているのかい? 確かに今のままなら少し前衛専属は難しいかもしれないけど、武器の調整をして前衛特化型に改良すれば大丈夫だと思うよ」
「いや……それもあるんだが」
それもある、が。なかなか自分の中のもやもやした気持ちが言語化できない。うまく言い表せられない。根拠もなにもない。ただの感情だ。でもそれを言語化しようと試みる。
……そう、俺は、頼城が、「頼城が前衛になるのがただ嫌」なんだ。だから「俺が前衛をしたい」と思っている。そう、向いていないと確定的に明らかな前衛を。俺の体格で前衛をやるのがどれだけ無謀なことか分かっている。そういう風に作られていないんだ。当たり前だ。けれど、俺は前衛がしたい。頼城を前衛にはしたくない。だから、俺が。
「……神ヶ原さん、例えばだが俺が重式をする場合、どういった武器が適していると思う?」
「えっ、重式かい? うーんそうだなぁ、重式は基本的に近距離だから剣になるんだけどね、体格に合わせると短かくて軽い刀身がいいだろうし、そうだなぁ、日本刀みたいなものになるかな。でもあんまり軽いと敵の攻撃を受け流せないし……薙刀みたいな感じがいいかなぁ。それで持ち手を頑丈にして……いやでもそれだと……」
ぶつぶつと呟き始めた神ヶ原さんは一分ほど考え込み、最終的に「試してみないとなんとも言えないけど、大太刀かなぁ」と結論づけた。
「大太刀……」
「あっもちろん大変なことは分かってるよ、でも不可能じゃなくて、身長と刀身の差が少なかったり逆転していても扱えないわけじゃないんだ。コツを掴めばなんとかなることもあるよ、訓練が必要だけどね」
「訓練次第でどうにでもなるのか」
「まぁ、前向きに言えばそうだね」
神ヶ原さんは待っていた。俺の体躯で重式は無理だとは言わなかった。技術者がそう言わないのであれば、可能なのだろう。
「……向いていないのは重々承知だが、重式をやってみたい、と思う」
「分かりました。斎樹くんに合うような重式武器を作ってみるね。じゃあちょっと採寸とか筋力の測定とかしようか」
そうして晴れて重式としてヒーローになったわけだが、結果は散々だった。初陣で敵の攻撃をまともに腹に受けた俺は胃の中のものをすべて吐き出し、無様に地面に転がって折れた肋骨が再生する感覚にさらに吐き気を催していた。
「巡!」
頼城がイーターに威嚇射撃をしながらこちらに駆け寄るのをピントが合わない視界の中に捉え、ばかやめろ、と口にするものの掠れた声は届かない。その威嚇射撃でイーターが距離を取ったからいいものの、敵の攻撃を受け地面に転がり、仕留められると思われた獲物の元に駆けつけるのは良策とは言い難い。
「巡、大丈夫か」
「い、いから、お前は、位置につけ、行くぞ」
「しかし巡、」
「い、いって言ってるだろ! 死ぬぞ!」
血反吐を吐き捨てながら再生の終わった腹をひねり、長刀を引きずり前に出る。イーターはこちらをじっと見つめて尾をゆっくりと振りながら標的を見定めている。好戦的なタイプだ。ちょっと挑発すればこちらに躍りかかってくるだろう。交戦地帯まであと少し。地面に転がってなどいられない。
「頼城、交戦地帯の方角から銃で誘導してくれ。間に俺が入って攻撃は通させない。着いたら俺が盾になるから頼城は脚を狙え、動きを封じ次第とどめを刺そう」
「了解した、無理はするなよ」
頼城が交戦地帯の方向に下がっていくのを音で確認しながら、その対角線上に入る。頼城が俺を避けて銃でイーターを撃ちつつ後退していくのを追い、イーターが頼城に攻撃を仕掛けたら間に入ってその爪を弾き返す。俺に狙いが定まりそうなら、再度頼城が銃や剣撃でイーターの気を逸らしイーターを誘導していく。そうして交戦地帯まで辿り着いた直後、開けた場所に標的である頼城が移動したのを見てだろう、イーターが大きく跳ね上がり頭上から攻撃をしかけてきた。
「頼城!」
走って攻撃の間に入ろうとしたものの間に合わない。頼城はイーターの挙動に気付いて回避行動を取ろうとしているが距離が縮まったあとのことを考えると牽制しておきたかった。長刀に力を込めるとバチバチと閃光が走る。武器に付与してもらった雷の属性によるものだ。ありったけの力を解放して武器を投擲する。電をまとわせた長刀は無事イーターの首に刺さり、敵は苦しみながら地面を抉って着地に失敗した。その間に頼城が片方の前足の腱を切り裂き、逆の前足で頼城を振り払おうとするのをバックステップで避けながら銃で何発も撃ち抜き、前足を使い物にならなくしていた。
「助かった巡!」
「まだ後ろ足がある、油断するな!」
駆けつけたもののイーターに刺さった長刀はとてもじゃないが抜けない。柄を握り、そのまま下に切り裂くかと思い力を込めたところでイーターが苦しんで首を振りもがいた。長刀を握っていた俺はその反動でぶん投げられて空を舞う。
「巡!」
頼城が落ちてくる俺をキャッチして即座に立たせる。丸腰の俺は頼城に任せるしかない。作戦はその時点で大崩れ。結局そのあと頼城が間髪入れずに切り込み、なんとか倒しきったイーターから武器を回収して初陣は終了した。
「ハハ、ザマぁないな」
「いや、あの投擲があったからこそ掴めた勝利だ。巡がいてくれて助かった。ありがとう」
晴れやかな笑顔で手を差し伸べられるが内心かなり複雑だった。ふたりとも手が血でかなり汚れている。リンクユニットを割った際にできた傷から出た血だ。傷は既に塞がっているが、流れた血はどうしたって残る。その血で汚れた手で、握手を交わした。
その時に気づいた。俺は頼城を守りたかったのだと。血を流させることなく、こいつが望むヒーローをさせてやりたいのだと。そのためなら頼城に預けることになったこの命など、惜しくないのだと。
気づけば夕暮れで、落ちかけた日光が至る所に反射してまばゆく瓦礫を照らしていた。金の目になってからというもの、光が眩しくてしかたがなかった。世界の至るところが眩しくて鮮やかで目が痛い。目をすがめて先を行く頼城を伺う。傷だらけで、ぼろぼろで、埃にまみれて、まっすぐに立って歩く背中。風にたなびく紺色の髪が、流星の尾のように見えた。
ふと頼城がこちらを振り返る。金と青の目が光っている。
「どうした」
「いや、初陣はどうだったかと思ってな」
「ハ、見ての通りだよ。向いていない。……でも、まぁ、やってみるさ」
頼城がそれを聞いて笑った。嬉しそうに。
「斎樹巡初陣の記念碑をこの地に建てようか!」
「やめろ!」
「なぜだ? 今日は記念すべき日だ!」
目を上げたときにはもう太陽は沈んでいた。
造りかけの建物が並ぶこの街の、煙がたなびく交戦地帯で、星のような男と並んで歩く。数々のサンプルの中で、きっと俺だけがこうなった。できそこないの失敗作でも、願うことは許されるだろうか。この星が消えないようにと願うことぐらいは、許されたいと思った。