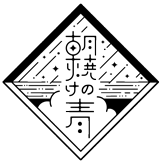ヒーローを始めてから、毎日レポートを書くようになった。それは毎日のように起こる戦闘や訓練での気づきをまとめる目的のもので、決して上手くはいかない自分の未熟さを、せめて得意分野の分析で補おうとしたのがはじまりだった。
「つまり、あまり見られたくはないもの?」
「……まぁ、そういうことになる」
柊は少し丁重な仕草でそのノートの束からひとつを手にとった。パラパラと数枚めくり、すごい、とため息を交えて口にする。
「ハハ、お前、単純に文章量だけで圧倒されているだろ? 中身はてんで未熟な重式の後悔ばかりだ」
「……確かに、俺はそんなに早くは読めないけど。でも巡くんが頑張っているのは分かるよ」
パラ、とめくられたそこには戦闘開始から終了までの陣形の遷移図が描かれていた。
「普通は、向いてない人は、こんなにしっかりと陣形を覚えながら戦えない」
「……まぁ、記憶力だけはあるからな」
「今見てもその時の風景が分かるよ」
柊が陣形の図を指先でなぞりながら目を伏せた。俺はなんだかむず痒くなって身じろぎをすると、まぁ、なんだ、と言い訳のようにボソボソと言い繕う。
「当時は重式の基本的な動きを基点にしていた。一年生で重式になる奴がいたらこれと似たような動きをするはずだ。参考にはなるだろう」
「ありがとう、巡くん」
柊が頭を下げてその後悔の束を持っていくのを、どこか内部に風が吹くような気持ちで見送った。
春が巡り、頼城が卒業していったその後に、新しく入ってきたヒーローたちの世話を柊が買って出てくれた。単純に後輩の世話というものが得意なのだろう。俺も最年長としてすべきことが山のようにあるはずだが、柊が喜んで育成役を引き受けてくれたものだから、今のところは呆けていることが許されている。
(あっという間だったな)
窓の外の桜吹雪を見ながらあのノートを書き始めた日のことを思い出す。ラ・クロワ学苑のヒーロー一年生として活動しはじめてすぐの頃、そこら中が痛む体に休むことが許されない絶望を、なんとかマシにしたくて始めたノートだ。一年生が遭遇する悩みに対する対処は一通りあれに書いてある。恐らく今読めば恥ずかしさでのたうち回りたくなるようなことも山のように書いてあるはずだ。それでもあのノートを引き渡したのは、柊が重式希望の生徒が突っ走り気味で、どうすればいいか分からないという悩みを打ち明けたからに他ならなかった。俺が出るべき所だったが、今まで自由にさせてきた柊に少しでも他ポジションの苦悩というものを分かってもらうべき時なのかもしれないと思い、今まで書き溜めたノートを明け渡したのだ。
俺が三年生になって、すべきことはなんだろう。上手く後輩を導くことができるのか——そんなことは到底できそうにない、とあの男の顔を思い出してため息をついた。
頼城紫暮は、おおよそ出来すぎるのだ。あんな化け物と自分を比較するものではない。頼城ならきっと、あんな無様なレポートなど作ることもないのだろう。しかし、そこまで考えてふとあの男が後続のことをなにも考えていないはずはないと思い至った。街を守るヒーローたちのことを、ヒーローを志す者たちのことを何よりも考えてきた男だ。自分のポジション、迅式になるはずの新一年生に対して何を残したのだろう。
こういう疑問はとっとと聞いてしまった方がいい。携帯を取り出すと履歴の中から電話番号を探し、通話ボタンをタップする。しばらく呼び出し音が流れたあと、スピーカーから流れてきたのは暴力的なまでの爆音によるモーター音だった。
「……ぐ……ちょ……はは!」
「なんだ頼城、聞こえない、ヘリにでも乗ってるのか?」
「そ……ま……す……!」
プツ。通話は途切れた。恐らくはヘリに乗っている。十中八九ヘリに乗っている。と、いうことはだ。
『巡! すまない通話を途切れさせてしまったな!』
出た。外からバラバラというヘリのプロペラ音が聞こえる。一年生がなんだなんだと物珍しそうに窓から身を乗り出しているのがちらほらと見える。ああ、頼城、ヒーローは引退したんだからヘリから飛び降りるなよ、と祈りながらその窓際の一員に加わって見守っていると、頼城はあろうことかヘリから飛び降り——落ちてこなかった。よく見ると背中に小型のプロペラのようなものを背負っている。かねてより開発していたという小型飛行装置が完成したのだろう。目ざとくこちらを見つけた頼城が「巡ー!」と手を振っている。なんてことだやめてくれ目立ってしまう。ひきつり笑いが浮かぶ自分の表情筋をとりあえずなだめて、校庭に降り立った元ヒーローを出迎えに昇降口まで小走りで向かった。